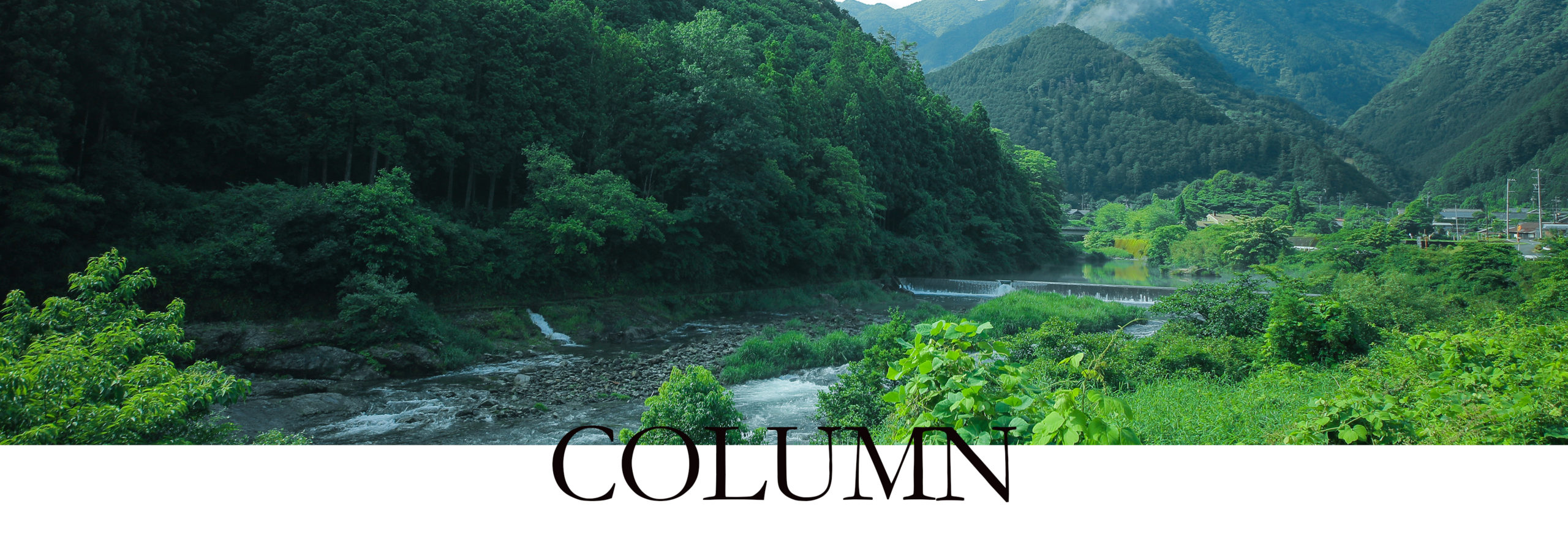
二月に入りバレンタインデーを過ぎたころから、寒さがゆるむように感じます。実際にはまだ寒いのですが、春の兆しの光の粒が空気に交じってくる気がするのです。もうすぐ春が来ますね。
一年前の春。京都にお嫁入道具を見に行きました。江戸時代に京都で、京屈指の豪商であった那波家からやはり豪商の柏原家に嫁いだ女性のものです。
所は京都市東山区。“江戸店持ち京商人”として漆器の「黒江屋」などを経営し、今に続く豪商家「柏屋」こと柏原家の旧宅。現在は「洛東遺芳館」として柏原家に伝わる美術品などが公開されており、この時は会館50周年記念の展覧会が開かれていました。
 産椅子
産椅子婚礼丁度の棚や箱などは、いずれも美しい光沢のある黒漆で、縁起の良い樹木などが蒔絵されていました。長い年月に色あせることもなく、昨日つくられたような保存状態です。そこに、那波家の家紋「丸に角立四ツ目菱」が、金で蒔絵されています。その家紋が、これでもかというほどたくさんで大きいのです。旧宅の一部屋に、三井家から嫁いできた夫人の鏡台がありましたが、そこにも三井家の家紋のひとつである桐の紋が散らされていました。それらを見ていたら、豪商同士が姻戚関係を結ぶということが、大資本同士の結びつきであったことや、これをもって嫁いだ女性は、その家紋の重みをずっしりと感じながら婚礼を迎えただろうことが、ひしひしと伝わりました。
まさに眼福でしたが、大名道具に負けない豪華な婚礼調度に驚き、文化力の高さや財力に圧倒され、京商人おそるべし…と思いながら松阪に帰りました。
 石水博物館「洛東遺芳館所蔵名品展 京商人の美意識」のチラシ
石水博物館「洛東遺芳館所蔵名品展 京商人の美意識」のチラシその時の展示には円山応挙をはじめ円山派の絵画が多かったのですが、「柏原家以外にも、三井家は円山派のパトロンでしたし、松坂の小津家にも円山派の絵画が多数あったことが知られています。商人の現実的な気質に写実的な円山派の画風が合っていたのでしょう」と桐田さん。また、婚礼調度のひとつ、華麗な貝合わせの貝と貝桶が目を惹きました。これは「雅な都の文化を背景に持つ京商人ならではのお道具で、伊勢国を代表する商家であった射和の竹川家から嫁いできた半泥子の祖母・政夫人らの婚礼調度の目録には、こういった貝桶などは見当たらないのです」との桐田さんのお話に、京商人、大坂商人、近江商人、伊勢商人などには、共通した商人ならではの文化があり、またそれぞれの地域ごとに違いがあることを知りました。きっと、商いの理念や方法にも、共通点も相違点もあったのでしょう。
松阪の歴史好きの人たちと話していると、「なぜ三井高利は松坂を出て、京都に行ったのか」という話題が出ることがあります。江戸でも大坂でもなく京だったのには、何らかの理由があるでしょう。呉服の仕入れのために京にいることが大事だった―とか、江戸には息子たちを置き、自分は上方の情勢をつかむため、大坂や近江に近く、都である京に移った―とか、あるいは、松坂では長谷川家はじめ近くの商家と仲が悪く嫌気がさして松坂を出たのだろう―とか、いろいろな説が出ます。京というまちの持つ魅力も大きいでしょう。高利が71歳の時、京で11番目の息子が、唯一妻以外の女性に生まれているのを知ってからは、「妖艶な京女の魅力にひきよせられたのかもしれませんよ」と茶々を入れたりしていますが、理由は一つではなく複合的なものだっただろうと思います。
そして、この柏原家の宝物を見ていると、高利は、京商人たちの間に自分を置き、その高い文化力と財力とを併せ持つ仲間に入りたいと願ったのだろうと思えてきます。富商たちの奥行きの深い世界に魅せられたことも、京に住んだ理由の大きな一つだっただろうと思うのです。
オランダから幕府に献上されたものらしいタペストリーが徳川家から三井家と伊藤家(松坂屋の前身)に渡り、それが祇園祭や長浜の大津祭の山鉾の懸装品となっているのだと聞いたことがあります。京の町衆が伊藤呉服店や三井本店から買い取った領収書が残っているとか。伊藤家は尾張徳川家に、三井家は紀州徳川家に、それぞれ多額の献金や貸し付けがあったそうで、タペストリーはそれに対する謝礼だったのではないかなどの推測がなされています。そして、伊藤呉服店と三井本店は、室町通りを挟んで向かい合わせにあったということです。そこにどんな物語があったのだろうと興味をそそります。
豪商同士は、商いでは厳しく競合しあったでしょうし、知識やセンスでも張り合ったでしょう。また一方では姻戚関係を結ぶなどして助け合ってもいました。商いは、大きくなるとお金儲けだけではなく、政治や文化も動かすようになっていきます。そして、人の世に浮沈はつきもの…
歴史の多くは為政者側から語られますが、商人側から見た歴史はまたちがう味わいがあるだろうと思います。ことに経済が発展した江戸時代以降は、商人のネットワークも発達し、現代人が思うのとは違う様相だったかもしれません。
半泥子と松阪のことは、次回にいたします。長引いて恐縮ですが…。
春が来たら、野に出ましょう。松阪の野も、もうすこしすると花盛りを迎えます。
洛東遺芳館
〒605-0907 京都市東山区問屋町通五条下ル3丁目西橘町472
TEL:075-561-1045 FAX:075-561-3651
https://www.kuroeya.com/05rakutou/
ぷらっと松阪 不足案内|2025.02.15
編集者 三重県の文化誌「伊勢人」編集部を経てフリーランスに
平成24年より神宮司庁の広報誌「瑞垣」等の編集に関わる
令和4年発行『伊勢の国魂を求めて旅した人々』(岡野弘彦著 人間社)他 編集