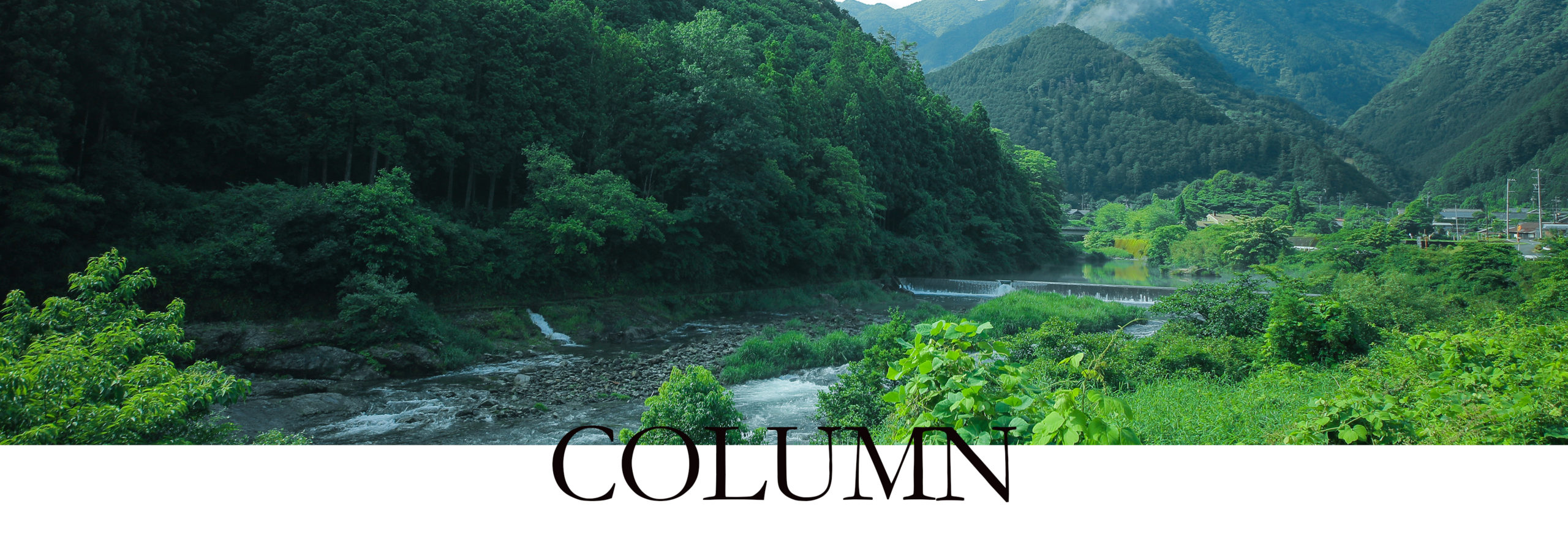
2008(平成20)年1月20日に始まった「古事記伝音読の会」もいよいよ17年目に入った。私の油断やコロナでの一時の中断はあったが、今は巻8、天照大御神が速須佐之男命の暴虐に驚きの天石屋戸にお隠れになられた所を読んでいる。
それまでの唱和もコロナ禍で出来なくなり、今は私が一人が読み、いささかの説明を付けるという形式に改めた。結果として進み方は早まったが、それでもまだ8冊目。主宰者の松井氏も逝き、参加者で鬼籍に入られた方も幾人ぞ。全44巻。末遙かなり、である。
表題から何から何まで、もちろん読み方の定まらぬ所もあるが、取り敢えず全部読む。
注釈書を音読するなど意味のないことと陰口を叩かれることもあり、憫笑、また不思議なことと呆れる人と様々である。
十数年も続くと、「本当に全部声に出して読むのか」と驚きをもって見られることが多い。逆に私が驚くのが、『古事記伝』を全部読む人の少なくなったことである。
さすがに古典の研究者は、若い頃には一度は通読しているだろう。だがその後は、殆どが必要個所を読むだけという人が多い。それも黙読で。
それでは『古事記伝』を読んだことにはならないのである。
『古事記伝』は宣長自身が、、
「己レ壮年より、数十年の間、心力をつくして、此記の伝四十四巻をあらはして、いにしへ学ビのしるべとせり」
『うひ山ぶみ』
と書くように、心力を尽くして書いた本である。
 本居宣長自画自賛像(部分)
本居宣長自画自賛像(部分)賀茂真淵と出会ったのが34歳の夏、その翌年正月から『古事記』研究に本格着手した。巻1.2の草稿となる『古事記雑考』の執筆もこの時期に始まったとすると、『古事記伝』起稿は1764(宝暦14・明和元)年と考えてよい。全巻終業は1798(寛政10)年6月13日。ざっと35年である。
その間、生業である医者の仕事を務め、歌会や講釈をし家政を取り仕切った。交友は広がり門人も増え、五人の子どもは成長する。
その僅かな時間を見つけて書き継いだのである。
『古事記伝』草稿本は、『古事記』中、下巻のものだけが残り、苦心した上巻部分は失われてしまった。
なぜ消えたのか。失われたのか。宣長研究者なら一度は考えるであろう「謎」である。
最近、私は上巻草稿は冊子形態であったとしても、反古の裏の書かれていて紙縒で仮とじした、殆ど紙の束のようなものではなかったかと考えている。
僅かな時間を見つけて、手近にあった紙に書いた、メモしたもので、文字通り、散逸したのではなかったか。
写真はその草稿本であるが、これらはまだ形が整っているほうだ。

『古事記伝』草稿は紙の束
そのような特殊な執筆形態なので、たとえば、「よし、今度は『続日本紀』宣命の注を書こう」と机にむかって執筆した注釈書とは訳が違う。
メモを取り、ああでもない、こうでもない。では斯くは考えられぬか、といろいろ思案する過程を取り敢えず形にしたのが『古事記伝』の草稿である。
この宣長の悪戦苦闘は沈思黙考ではなかなか分かるまい。それよりは、執筆の流れに乗る、つまり一々に停滞せず読み進めるほうが見えてくるのではないかと私は考えた。
さて、今年2025年2月は、版本8巻46丁表「祷白而(ねぎまをして)」から始まった。 いよいよ岩屋戸開きのハイライトシーンである。天児屋根命が布刀詔戸言(ふとのりとごと)を申し上げる個所である。
この時に奏上された言葉の麗しさは『日本書紀』にも、
とあるように、隠れていた天照大御神の心をも動かすほどであった。だが、今も神前で奏上される「祝詞」の始まりとも言えるこの時の言葉は、どこにも記録されていないことを宣長は嘆く。
この、天照大御神の心を動かしたのが「言葉」であることから、宣長の連想は、『万葉集』で柿本人麻呂、山部憶良が歌に詠んだ「言霊の幸ふ国」、「言霊の助る国」ということばへと展開する。
 『古事記伝』版本8巻〈言霊〉
『古事記伝』版本8巻〈言霊〉さて此の時に祷(ねぎ)白(まを)せる辞(ことば)は、祝詞(のりと)の始(はじま)りにて、いとも古文(ふること)にて麗美(うるはし)かりけむを、此(ここ)に載らず、世に伝はらぬは、甚々(いといと)憾(くちをし)きわざなりかし
【世々の学者、此の段を説くに、たゞ諸神の心の誠款(まこと)なりしことをのみ云て、辞(ことば)のことをば等閑(なほざり)にし、凡て古言をば、尋ねむ物とも思ひたらぬは、いたく道の意に背(そむ)けり】
『書紀』に、此の広き厚き称辞(たたへごと)を聞(きこ)しめして、大御神の曰(のりたまは)く
「頃者(このごろ)、人多(さは)に請(まを)せども、未だ若此(かく)言(こと)の麗美(うるは)しきは有らずとのりたまひて、乃ち磐戸を細めに開けて」
とあるを見るべし。もはら言辞(ことば)に感(めで)たまふにあらずや。
「言霊(ことたま)の幸(さきは)ふ国」、
「言霊(ことたま)の助(たすく)る国」
と云る古語も、思ひ合されていとたふとし」
『古事記伝』8-47
今や失われ、聞くことの叶わぬ天児屋根命の祝詞を想う宣長の心は切であった。
そして「ことば」の持つ力への思索はさらに深められていく。
「古事記には、たゞ歌をのせんためのみに、其事を記されたるも、これかれ見えたるは、その歌のすぐれたるが故なり、さてかくのごとく歌は、上代よりして、よきとあしきと有て、人のあはれときゝ、神の感じ給ふも、よき歌にあること也、あしくては、人も神も、感じ給ふことなし、神代に天照大御神の、天の石屋(いわや)にさしこもり坐(まし)し時、天ノ児屋根ノ命の祝詞(のりとごと)に、感じ給ひしも、その辞のめでたかりし故なること、神代紀に見えたるがごとし、歌も准へて知ルべし」
『うひ山ぶみ』
「ことば」、そしてその精華とも言うべき「歌」への絶対的な信が宣長にはあった。
「言霊が幸は(わ)う」とは、ことばの力が全開、最大限に発揮されるということである。我が国というかこの国土に住む人は、ことばの力を恐れた。「こと(言)」として発せられると、それは「こと(事)」として現実のものとなるので、軽々しく声に出すこと、それを「言挙げ」という、を慎んだ。
葦原の 瑞穂の国は 神ながら 言挙げせぬ国 しかれども 言挙げぞ我(あ)がする 事幸く ま幸くませと つつみなく 幸くいまさば 荒磯波 ありても見むと 百重波 千重波しきに 言挙げす我(あれ)は 言挙げす我は
反歌
敷島の 倭の国は 事霊の たすくる国ぞ まさきくありこそ
『万葉集』13・3253・3254「柿本人麻呂歌集」
旅立つ人に、どうかご無事でと言祝ぐ歌だと言う。
私の話も第30話、今回を以て終了する。このあとの展開は、
「抑意(こころ)と事(こと)と言(ことば)とはみな相称〔かな〕へる物にして上ツ代は、意も事も言も上ツ代、後ノ代は、意も事も言も後ノ代。漢国(からくに)は、意も事も言も漢国なる」
という、宣長のテーゼ、そして有名な
「姿は似せがたく、意は似せやすし」
へと進むことを考えていたのだが、今頃になって、表題が「カチっと松坂」であることに気づいた。
原稿では、「カチッと松坂」で書いていたのだが、おそらく一等最初、タイトルを決めるときに間違って送信したのだろう。
こんな迂闊なことでは、ことばの力を絶対的に信じた宣長先生について語り続けることは出来ぬと、一旦、仕切直しとすることにした。
お読み頂いた皆さまに、感謝します。
ぜひ松阪の地に立って頂き、土地の力〈トポス〉を感じてください。
そよぐ風の音、城跡から今も跳び続ける落花、その中に宣長の声が静かに流れているのが、聞こえてくるかもしれません。
事幸く ま幸くませ
カチっと松坂 本居宣長の町|2025.03.1
前 本居宣長記念館 館長
國學院大学在学中からの宣長研究は45年に及ぶ
『本居宣長の不思議』(本居宣長記念館) 『宣長にまねぶ』(致知出版社)など著書多数