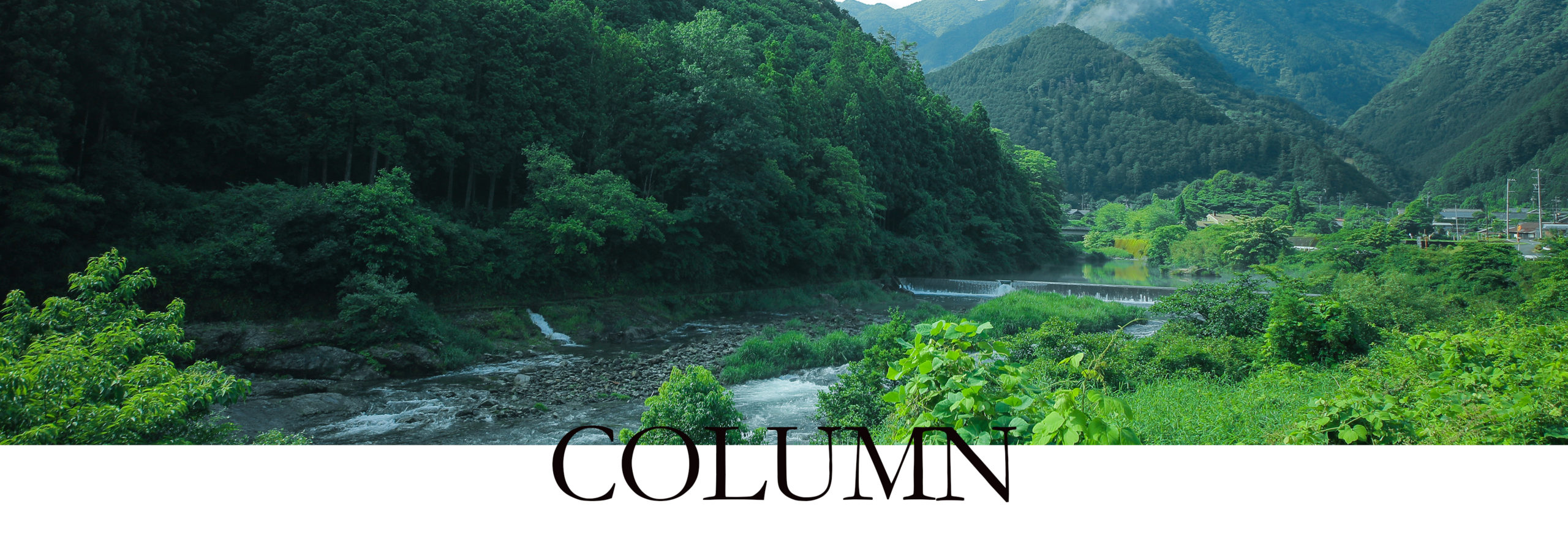
春が兆したと感じたのも束の間、はやくも爛漫へと移ろっていきます。
“兆す”という言葉が好きです。“萌す”とも書きます。なにかが起こりそうな気配がすること。まさに芽が出ようとする勢いだけが発せられる瞬間のことです。“予感”というよりは少し現実的でしょうか。どんなことも、実際にはまだ何も起きていないけれど兆しが感じられるとき、ときめきだけが起きるあわいが、一番いい瞬間だと思うのです。
「兆」という漢字は、亀甲や獣骨を熱して占う亀卜・太占のひび割れの形からできた文字で、片側だけに亀裂があるのが“卜”、両側にあるのが“兆”だと聞きました。占いで亀の甲に小さく走った亀裂を何の兆しとみるか… よくないことなら急いで封じねばなりませんが、胸をときめかせるような良いことの兆しであってほしいものです。
日本の歴史の中で、人々が最も大きな兆しを感じていたのは幕末ではないでしょうか。大塩平八郎の乱が起き(1837)、中国がアヘン戦争で侵略され(1840-1842)、ペリーの黒船が浦賀に来航し(1853)、国内は混沌としてエネルギーが溢れ、鎖国の枠の中から海外への目が開けていく。いずれ何か大きな変革が起こるに違いなく、でもまだ、はっきりとは現れていない。兆しを察知した薩摩藩や長州藩では幕府に内緒でイギリスに留学生を送っていたそうです。たくさんの地点で、ヒヨコが卵の中から殻をつつくように、大変革に向かう動きが起こっていました。
そんな時代を生きた、とても気になる3人の兄弟がいます。勢州射和の竹川家に生まれた、竹川竹斎(1809‐1882)と弟の信義、信親です。竹川家については、この「ぷらっと松阪」の4,ぼたん雪と母の力でも少し触れていますが、改めてご紹介しましょう。
この三兄弟がうまれたのは、射和の竹川家の分家、東竹川家です。丹生で生産された水銀を源として、多気の相可や射和、中万など櫛田川沿いの地域は古くから商いが発達し、豪商と呼ばれる家々が軒を連ねていました。竹川家もその一軒で、もとは滋賀の浅井家の一族、丁野友政を祖とする武家でしたが、天正年間、織田信長に敗走し、明和の竹川に住んで竹川姓を名乗ります。その後、射和に移って商業をはじめたと言われます。
兄弟の父・政信は東竹川家の6代目。本居宣長の門人でもある教養人で、母の菅子は、伊勢の神職であり国学者でもあった荒木田久老(ひさおゆ)の娘でした。

嘉永6(1853)年、黒船が浦賀に現れると、竹斎はすぐさま「護国論」という本を書きます。黒船の来航に慌てふためく幕臣のありように怒っての執筆だったということです。ここには、日本の国防をどうすべきかの具体的な案も書かれています。それが書けたのは、各藩の経済事情をつかんでいた両替商ならではの視点もあるでしょう。また、ペリーの黒船が外輪船で古いタイプであるなど外国の軍艦についての知識も書かれており、鎖国の中でも、竹斎が海外についての知識を持っていたのが分かります。実際に、竹川家には天保10(1840)年に竹斎が弟の信親とともに書き写した天文方作成の世界地図などが残されており、竹斎らの視線はすでに海外に向かっていたのが分かります。竹斎は、函館の豪商・渋田利右衛門から勝海舟を紹介され、かねてから海舟のパトロン的な存在になっていましたが、この「護国論」は、勝海舟によって幕府の要人たちに伝わり、竹斎は目付の大久保右近将監や勘定奉行の小栗上野介忠順らに面会を求められ、意見を聞かれるようになります。また、茶の湯においても、当時裏千家の家元であった玄々斎と師弟ながら親しく交流し、裏千家の茶室・今日庵を使って茶事を開くほどの才人でした。
次男の信義は、やはり櫛田川沿いの乳熊郷(現在の松阪市中万町)にある竹口家に養子に入っています。竹口家は、(株)ちくま味噌として現在に続く豪商で、慶安年間(1648-51)に江戸に進出し、幅広い商いをしていました。元禄十五年(1703)12月14日の吉良邸討ち入りの後、深川永代橋のほとりの乳熊屋に立ち寄った赤穂浪士に甘酒(清酒ともいわれる)をふるまった逸話が残されているなど、江戸の文化に深く根を張った有名店です。信義も竹斎とともに勝海舟やパークスらと親交を深めていました。ほぼ江戸にいた信義は竹斎の重要な情報源であったのでしょう。現在も商いは幅広い業種にわたっていますが、コロナウィルスのパンデミック時に、いち早くPCR検査の会社を立ち上げて東京の各所に検査ステーションを設置したことなど、機を見るに敏な伊勢商人の面目躍如という気がします。
下の弟・信親が養子に入って継いだのが國分家で、八代勘兵衛を襲名しています。射和の東竹川家の向かいに屋敷を持つ豪商で、現在の国分グループ本社㈱となっています。この家も歴史は古く、國分伊賀守の子孫・國分甚太郎を初代とし、正徳2年(1712)に四代勘兵衛が土浦に醤油醸造業を立ち上げ、日本橋に店を持ったのを創業としています。「亀甲大」の印で知られ、嘉永6(1853)年の「関東醤油番付」では「行事」として別格に扱われるほどの隆盛でしたが、明治維新後は醤油から食品卸業に大きく方向転換し、缶詰のほか、広く食品を扱って現在に至ります。最高級の食材を詰めたと評判の「缶つま極」シリーズの「エスカルゴ・ド・ブルゴーニュ」は、松阪市にあるエスカルゴ牧場のエスカルゴが使用されているそうです。世界で初めてエスカルゴの完全養殖を成功させた牧場だそうで、やはり伊勢商人ならではの意欲的な商品開発でしょう。信親も、兄たちと足並みをそろえるように、来日したアメリカの宣教師・ヘボンと親交を結び、製茶貿易に乗り出しています。ヘボンは信義とも深い親交を結んでいました。三人の兄弟はしっかりと兆しをつかみ、次への準備をしていたのです。
竹川屋は幕府御用の両替商であり、竹斎は幕府の要人たちと深い関りを持ったため、討幕派から暗殺目標に指名されるほど有名になってしまったこともあり、竹川屋は幕府と命運をともにしましたが、竹口家、國分家の店は幕末・維新の混乱を乗り切り、現在も繁栄を続けているのは前述したとおりです。ちくま味噌も、国分グループ本社も、あちこちに様々な社屋がありますが、創業から300年を超えた今も、最初に店を開いた同じ場所、竹口家は永代橋の畔、国分グループは日本橋に、変わらず本社を構えているのは素晴らしいと思います。そしてまた、竹川家、竹口家、國分家の三家とも、松阪の櫛田川添いの射和や中万に、昔のままの姿で旧宅を保存されているのは、さらに素晴らしいことだと思います。幕末から維新を乗り超えた、あっぱれな3兄弟の功績大と言えるでしょう。
けれど、あっぱれだったのは男兄弟だけではありません。この3兄弟には、3人の姉妹がいました。



彼女たちもそれぞれ大きな商家に嫁いでいます。当時の一般女性について詳しい情報はよくわからないことがほとんどなのですが、一番下の娘・琴(嫁いで政と改名)は、大した女丈夫だったことが伝わっています。彼女は津の豪商・14代川喜田久太夫政明(石水1822-79)に嫁ぎました。石水は、前回・前々回とその周辺を語ってきた川喜田半泥子の祖父にあたり、石水博物館の名はその号にちなんでいます。石水も竹斎らに負けない豪商の主であり、知識人で、津の文化の中心的な存在でした。石水と政の間には、息子の政豊(1851-79)がいました。そして政豊は妻・稔子を迎え、明治12(1879)年、半泥子こと政令が誕生したのでした。しかし、同じこの年、石水と政豊が相次いで亡くなります。政豊は29歳でした。夫と息子を失った政は、悲嘆にくれたでしょう。でも、彼女は長くは泣いていられませんでした。彼女は自身で川喜田の家を守る決意をします。まだ18歳と若かった稔子を、別な人生を歩ませるため実家に帰し(のちに再婚)、自身の手で孫を育てます。1歳で家督を相続した半泥子は、銀行の頭取でありながら、茶道や陶芸にも秀でた数寄者に育ちます。そこには、川喜田家の家風や血筋もさることながら、竹川家の3兄弟の影響を感ぜずにはいられません。少なくとも、事業と茶道と陶芸という取り合わせは、大伯父の竹斎と同じです。晩年の竹斎は、幼い半泥子を気遣って、たびたび川喜田家を訪れたようですし、半泥子も政に連れられて射和を訪れたでしょう。豊かな名家とはいえ、あるいはそれゆえに一層、夫や息子を失い幼い孫を育て上げる使命を負った政の悩みは深く大きかったに違いありません。誰よりも信頼できるのは実の兄たちだったでしょうし、孫にも、目指すべき男性像として導いたことでしょう。明治32(1899)年、半泥子が21歳の誕生日に、政は手紙を渡しています。その最後にある「われをほむるものハあくまとおもうへし、我をそしるものハ善知しきと思へし、只何事にも我れをわすれたるが第一也」という言葉は有名ですが、厳しく自身を律することを教えた政の強い愛が溢れています。政の教育によって、半泥子は実業家としても文化人としても立派に育ち、さらに、自由な精神を持つ芸術家としても活躍しました。半泥子は、この遺訓を生涯ポケットに入れていたということです。政もまた、あっぱれな女性でした。
さて、ようやく半泥子と松阪のかかわりまで話が至りました。
今月1日の「カチっと松坂」で吉田さんが書かれていますように、吉田さんと私のそれぞれのページは今月で終了し、新年度からは二人で「松坂権輿雑集」を読んでまいります。寄り道し、脇道にそれながら、江戸時代の松阪を歩く気分で進める予定です。引き続き楽しんでいただけると幸です。
ぷらっと松阪 不足案内|2025.03.15
編集者 三重県の文化誌「伊勢人」編集部を経てフリーランスに
平成24年より神宮司庁の広報誌「瑞垣」等の編集に関わる
令和4年発行『伊勢の国魂を求めて旅した人々』(岡野弘彦著 人間社)他 編集