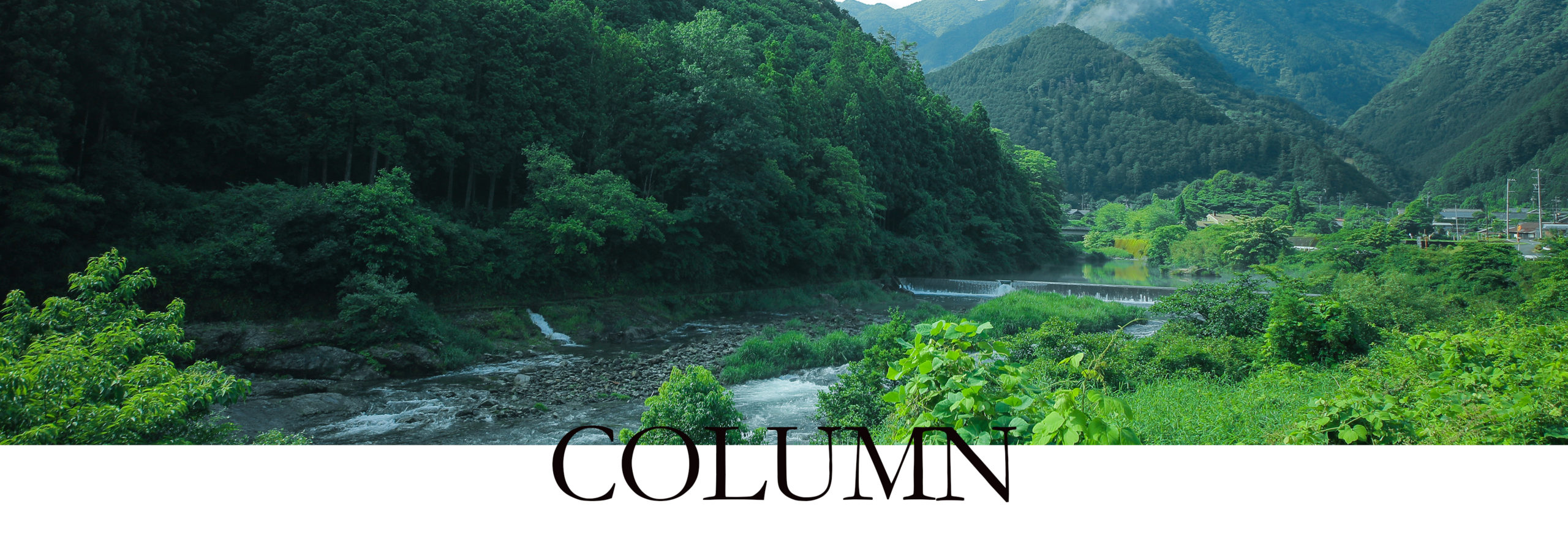

『松坂権輿雑集』 本居宣長記念館蔵
本居大平による写本。表紙は『松阪雑記』で、内題は『松坂雑集』。
「雑集」が「雑記」になり、「坂」と「阪」が混在。「権輿」は省略されている。
悦:吉田悦之 ほ:堀口裕世
悦:『松坂権輿雑集』は江戸時代の松坂について記された歴史書というか地誌で、皆便利に使っているけど、きちんと読んだことはなかったね、という反省から、「勢州松坂会」というグループで月に2回、集まって読んでみようということになったのが、ことの始まりでした。そして、その成果というか途中経過を、古きよき時代の松坂案内として載せさせていただこうということになりました。
ほ:恥ずかしながら私は、この本の存在を知りませんでした。お誘いいただいて、皆さん松阪の歴史に詳しい人ばかりとのことで、勉強させてもらおうという気分で参加しました。
悦:メンバーはみんな、松阪の歴史には一家言あるものの、知っていることにはむやみに詳しく、関心がないことにはまったく興味を示さないところもあるので、穴ぼこだらけの読書会ではありますね。
ほ:この会で、歴史というのは、少し知ると更に謎が増してゆくものだということを知りました。疑問に思ったところを皆さんに聞くと、いろいろな発展はあるもののまた次の疑問が出てきて、最終的にはわからないあなぁ…という結論になることが多かったですから。この会では、読み方などはあまり気にせず、大体の意味が分かればよしという考え方で、それぞれが持っている情報を出し合うことを重要視しています。会の活動は現在も続いていまして、いろいろ貴重と思える情報が出てきました。話し合うだけで過ぎていくのはもったいないと思っていましたので、こうして発表の場ができて良かったと思います。
悦:「注釈」や「解読」とはおこがましくて言えるものではありません。読まれた方からご批判やご教示をいただいて、新しい知見を得ることができるのではないかと期待しています。
ほ:炎上覚悟、反論上等、ですね。
悦:そこまで過激ではありません。ついつい口が滑ることはあるかもしれませんが。
悦:さて『松坂権輿雑集』は、伊勢平野の、小さな丘があるだけの、何もないところに、突然「松坂」というまちができた、その過程や、江戸時代のこのまちの様子を描いた唯一の書物です。
ほ:この本が書かれた頃の松坂は素晴らしい町だったのでしょう。
悦:そうですね。素晴らしいかどうかはともかくも、活力に充ちた時代でしたね。戦国時代の末に突然この町が誕生し、江戸時代に江戸店持ち商人の活躍で経済的に繁栄し、それにつれて文化の花が開きます。この町に生まれた本居宣長は、「松坂は、ことによき里にて、里のひろき事は、山田(伊勢市)に次ぎたれど、富る家多く、江戸に店といふ物を構えおきて、手代といふ者を多くあらせて、商いせさせて、主人は、国にのみ居て遊びおり、うわべはさしもあらで、内々はいたく豊かに奢りてわたる」(『玉勝間』)と書いていますが、まさにその「よき時代」の様子がこの本に記録されているのです。松阪在住の方はもちろん、この町を訪れる方にも、ちょっと覗いていただけば発見があると思います。この記事を知って町を歩けば、景色は一変しますよ。
ほ:はい、松阪には江戸時代の面影を宿していると思える場所もまだ残っていますので、読まれた方に楽しんでいただけるといいと思います。今、「松阪の歴史」とされていることの多くがこの本に依っていますね。
悦:そうです。今も町の各所に地名の由来を書いた柱が立っていますよね。それは、殆どが『権輿雑集』から採ったものです。
ほ:その地名の由来もですが、読んでいくと、これって本当かな…?とあやしく思う箇所もでてくるんですよね。
悦:疑い深い人ですね。確かに、年代など辻褄が合わない箇所もあります。奇妙な説もあります。たとえば、白粉町。地名の由来は白粉を商う店が三軒あったからだ。だがそれも無くなり、今は煎餅屋が多い。これは次郎助がはじめたのが最初だ、なんて言う記事は、今となっては検証は難しいけど、そう思って歩いてみると楽しいですよね。
ほ:白粉町を歩いてお菓子を買おうと思っても、今は町の入り口にコンビニがあるだけですけどね。
悦:私が子供の時には、まだ駄菓子屋が一軒ありましたが。それはともかく、巻1に「町中掟の事」というのが出ています。今、松坂の歴史を語る時には、百人が百人ともに引く史料ですが、この本にしか出ていないのです。
ほ:基本史料ということですね。だから本居宣長や三井家所蔵のものなど写本がたくさんあるのですね。
悦:この写本がなかなか役に立つのですが、それは追々説明するとして、基本史料、まさにその通り。だから、『南紀徳川史』という紀州徳川家の基本史料集にも丸ごと載せられているのです。ただ出版は遅れて、大正8年になってからでした。
ほ:では、会での話を振り返りつつ本文を読み下し、それについて出てきた情報や謎の部分を、その時々の形で話し合っていくということで進めましょうか。
悦:いいでしょう。テキストは『松阪市史』を使用しています(『松阪市史』史料篇、近世地誌2)。原文が見たい人は『市史』をご覧ください。表記について、異体字などは適当に処理しています。漢文は訓読しました。本来なら、ここで凡例を示すところですが、「雑集」の「雑感」なのでそんな大仰なものはやめましょう。まったく手も足も出ない箇所もありますが、そこも「判りません」と済ませてご容赦いただくこととします。
ほ:ま、細かいことは置いといて、ベル‐エポックの松坂へGo!です。
 白粉町に立つ道標。説明文は『松坂権輿雑集』に依っている。
白粉町に立つ道標。説明文は『松坂権輿雑集』に依っている。悦:まずは書名のことを話しましょう。
ほ:タイトルは「松坂権輿雑集(まつさかけんよざっしゅう)」ですね。
悦:「松坂」は、「まつざか」と濁音で言っていた可能性が高いです。「大坂(阪)」は江戸時代は「おおざか」と言っていました。それと「ぞうしゅう」が正しいと思いますよ。
ほ:市史の解題には「ざっしゅう」ってフリガナがありますが…?
悦:「雑」の字をザツと読むのは意外と遅れます。たとえば「雑談」という言葉がありますね。これを寛延3年(1750)年、まさに『権輿雑集』の時代ですが『懐宝節用集綱目大全』という辞書では「ざうたん」と読んでいます。これが「ざつだん」となるのは、明治23年の『増補東京節用集』あたりからです。「ざっしゅう」でももちろんいいのですが、おザツニではなくお雑煮(ぞうに)を食べているなら「ゾウ」と読みましょう。雑木、雑巾、雑色など皆ゾウですし、和歌の部立ても、恋や四季や挽歌でないものは雑(ゾウ)の部でしょう。
ほ:はい。では「松坂権輿雑集(まつざかけんよぞうしゅう)」ですね。
では、この「まつざかけんよぞうしゅう」の「松坂」ですが、今の三重県松阪市よりずっと狭い地域ですよね。
悦:松坂城の周辺ですね。城とともに整備をされた一帯です。私たちの年代なら、「旧市街地」などと呼んでいました。
「権輿」は「けんよ」と読み、物事の始まりを言います。「輿」は人が担ぐ車、つまりお神輿です。神さまの乗り物ですね。輿駕は天子の乗り物です。ヨロンは今は世論と書きますが、本来は輿論で、世間一般の人々が担ぎ出す意見のことですね。
ほ:「松阪市史」につけられている「解題」では、「権」ははかりの重りを指して、「輿」は車の荷物を乗せる部分を指し、いずれも作り始めるとき最初に作る部分なので、物事のはじまりを言う、というようなことが書いてありました。また、タイトルを「権輿」を省いて『松坂雑集』としている写本も多いようです。
悦:つまり、この書名は、松坂の始まりについてのいろいろな話を集めた、という意味でしょう。
ほ:いろいろな話が混ざってる「雑」なところが面白いですね。では序文へ参りましょう。
ほ:原本では漢文ですが、読み下しました。意味としては、南勢飯高郡松坂は、一志郡の松ヶ島よりここに移し、改名したまちである。天正16年(1588)から宝暦2年(1752)までの165年間の事跡を、11の部に分け6冊の冊子として、絵図を一枚つけ『松坂権輿雑集』と題した、ということですね。「松阪」と「松坂」、両方使われていますね。
悦:漢字表記は、どうでもよいというのが、江戸時代、大方の知識人の態度ですね。
ほ:その人たちの方が漢字には詳しいはずなのに。
悦:詳しいから、表記にはこだわらないとも言えるでしょう。さて、松ヶ島や町を移したことについては後の文章で出てきますので、ここでは年号に注目しましょう。天正16(1588)年は、いわゆる松坂開府の年ですね。そして、宝暦2年(1752)は、これは著者・久世兼由が自序を書いた年です。この時代は文化史的に面白い時期です。
ほ:松坂の繁栄した時期でしたね。
悦:それだけじゃなく、日本史の上でも重要な転換点です。18世紀は「文化東漸」期です。それまでの文化の中心は京、上方でしたね。やがて江戸の町が出来て、人口やお金も江戸に集まってきた。すると文化もゆっくりと江戸に中心が移っていくのです。これを「文化東漸」と言います。この宝暦年間は、西から東に移っていく分水嶺なのです。松坂では、魚町の長谷川家では木綿の商いを分家に任せ、本家は金融業中心の営業に切り替えていますし、この年の3月には、23歳の本居宣長が医学修業のため松坂から京に上っています。
ほ:文化の中心が京都から東に移って行くのに、宣長は逆行ですか。
悦:いや文化の表層が東に移ったのであって、学問をするなら京都というのは、まだ有効な時期、賢明な判断だと思います。少し前の話ですが、賀茂真淵は京都で勉強して、江戸で就職しています。
ほ:「松坂官下」というのは、松坂の役人の管理下にある地域ということですか。
悦:松坂城下という意味でしょうね。「陰」というのは隠居しているということかな。
ほ:退職して時間もできたので、歴史の本でも書いてみようか…という感じですか。今も同じような人多いですね。
悦:勢州松坂会など、まさにそのような人の集まりです。
ほ:この久世兼由についても「解題」に「兼由は、通称定右衛門。貞享四年(1687)松坂殿町同心町住みの町奉行組同心・村瀬武右衛門信休の二男(母は紀州藩士・高橋氏の女)に生まれ、十七歳の時、同町の同じく町奉行組同心・久世弥一郎の養子となった。」とあります。同心町というのは、殿町の、今、原田二郎邸のあるあたりですか。原田二郎も同心だったのでしたね。
悦:『原田二郎伝』によれば、二郎のご先祖五代原田平兵衛は宝暦12(1762)年、和歌山藩に仕え、松阪町奉行組の同心となり、七石二人扶持の俸禄を受けたとあります。
ほ:宝暦12年なら、残念ながら『権輿雑集』以後ですから出てきませんね。
悦:ついでに言いますが、この『原田二郎伝』上下二冊は貴重な史料や写真が載った本ですから、ぜひ御覧になることをお奨めします。さて、久世兼由については、息子の篠川恒斎の手記が詳しいですね。やはり『市史』の解題に載っています。それによれば、実直な性格で、学問を好み、医術にも志し、松坂の医者・小泉見庵や中谷専庵、さらには松本駝堂にも入門したとあります。駝堂は本草学者で、蘭学の心得もあった人です。きっと兼由も学問の幅も広かったのでしょう。
ほ:何にでも関心を持つ人だからこの『権輿雑集』も豊かな内容になったのでしょうね。
悦:先ほどさらりと読まれた序の最後、「時に宝暦二年壬申の冬十一月甲子」ですが、宝暦2年が1752年に相当する。干支では「壬申」、「みずのえさる」、「じんしん」と音読しても構いません。ちなみに有名な「壬申の乱」は西暦672年です。
ほ:大友皇子と大海人皇子が皇位継承を争った戦いですね。
悦:このように干支は、十干十二支を組み合わせて年月日を数えるやり方です。60年で一巡して最初に戻るので「還暦」と言います。大宝令で元号使用が規定されますが、一般では日常的に使われていました。ここで「十一月甲子」とあるのは、11月の甲子の日ということですが、手元の本では甲子が何日かは分かりません。この年の伊勢暦でもあればすぐにわかるのですが。『権輿雑集』を書き終えて序文を認めた大事な日ですから、疎かには出来ません。
ほ:ネットで調べて見ると…。宝暦2年(1752)壬申の年11月の甲子の日は7日ですね。
悦:ネット恐るべし…。
ほ:この年、兼由は66歳で、その13年後の明和2年(1765)に75歳で亡くなっています。本文に至る前に、ずいぶん長くなってしまいました。では、次回から『松坂権輿雑集』第一 御城郭之部 に入っていきましょう。
 松阪市殿町 昔の同心町付近
松阪市殿町 昔の同心町付近
『松坂権輿雑集』を読んでみた|2025.04.1
前 本居宣長記念館 館長
國學院大学在学中からの宣長研究は45年に及ぶ
『本居宣長の不思議』(本居宣長記念館) 『宣長にまねぶ』(致知出版社)など著書多数
編集者 三重県の文化誌「伊勢人」編集部を経てフリーランスに
平成24年より神宮司庁の広報誌「瑞垣」等の編集に関わる
令和4年発行『伊勢の国魂を求めて旅した人々』(岡野弘彦著 人間社)他 編集