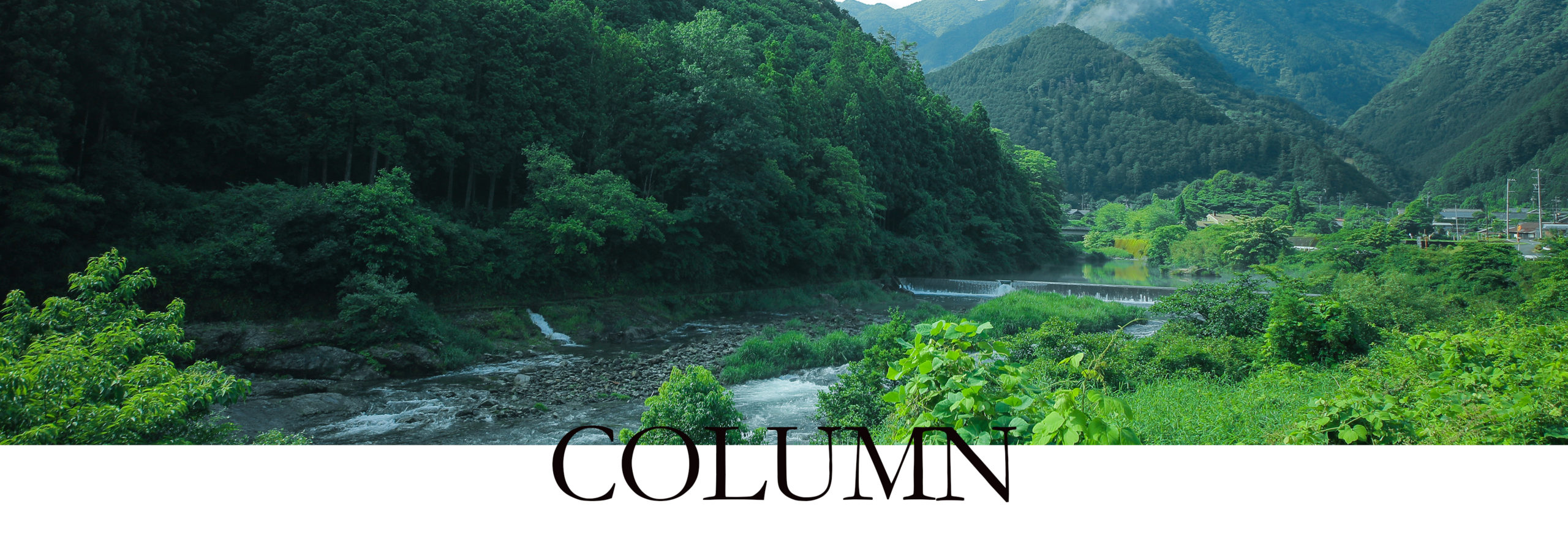
悦:吉田悦之 ほ:堀口裕世
ほ:さて、3回目を迎え、今回は蒲生氏郷についてです。早速読んでみましょう。まずは本文です。
蒲生飛騨守氏郷之事
一、蒲生飛騨守氏郷は、天正十二甲申(1584)の年、太閤秀吉の命に依り、本知一倍の加増にて江州日野より一志郡松ヶ嶋へ移城す。同十六子(1588)年、右松ヶ嶋城を四五百森に移し、松坂と改む。小田原の軍功に依り而、同十八庚寅(1590)年六十万石と成て奥州会津へ移城す。同十九卯年米沢領加増、都合百万石に至るの由語り伝ふ。
ほ:この章は、氏郷について書かれています。松坂開府の祖として、この町では格別の人ですが、本文としては上記だけです。内容は、蒲生飛騨守氏郷(1556-1595)は、天正12(1584)年に、秀吉の命で日野から松ヶ嶋へ移城し、つまり転封(てんぽう)、国替えですね、同16(1588)年に四五百森に城を移して松坂と改めた。小田原の軍功によって、同18(1590)年に60万石となって奥州会津へ移る。同19年米沢領を加え百万石に至った、とあります。「本地一倍」って、「倍」ってことでしょうか?「人一倍」は「人よりたくさん」という意味ですよね。それから、知行何万石というのは、この後も出てきますが、数字が微妙に変わりますが、あいまいなものなんでしょうか。
悦:戦国期から江戸時代、土地の生産力は「石高(こくだか)」であらわします。ただ検地以前は村の境界も曖昧です。一つの村でも、その土地を所有する領主が何人もいる場合もあります。さらに所領となると、武力で支配地を奪い合う日々ですから、実際どれだけあるかは誰も分からないというのが本当のところ。これはなにも蒲生氏郷に限った話じゃありません。それが織田信長、そして豊臣秀吉の天下統一、太閤検地で急速に信頼度が高まっていきます。ここの「本知一倍」は、倍ぐらいってことでしょう。
ほ:この後の付箋に、「八万石が十八万石になった」と書かれていますね。
悦:この記述については次で述べることとします。私が永年勤めた本居宣長記念館は松坂城址にあり、氏郷さんの築いた城で仕事をしていたから、多少の敬意はもっております。けど、複雑な思いもあり、詳しくもない、と最初におことわりして、蒲生氏郷の石高の変遷を述べてみますね。1570(元亀元)年、織田信長から、父蒲生賢秀・氏郷宛でこれまでの領地が安堵されます。
ほ:そうでした。ご先祖さま伝来の “氏郷嫌い”というか“信長勢嫌い”でしたね。「安堵」って、認められたということでしたね。
悦:そうです。その上で、没収した小倉氏の所領を含めた5500石余が給付されました。さて、「これまでの領地」が安堵されたといいましたが、では南北朝の頃から近江の土豪として出てきた「蒲生氏」がはたしてどれだけの石高を持っていたのかは、よく分かりません。支配地はだいたい分かりますが、群雄割拠というか戦国時代ですから実効支配しているか否かで、大きく変わっていきます。1584年に伊勢国松ヶ島に移ったとき、つまり今問題となっている時ですが、氏郷の伝記では、12万石になったとある。
 蒲生氏郷像 本居宣長記念館複製
蒲生氏郷像 本居宣長記念館複製
ほ:「本知一倍」はもとの知行の2倍ですから、逆算すると日野時代は6万石となるわけですね。
悦:これについて、『近江日野の歴史』第2巻ではこんな風に書かれています。
「一般に、近江での蒲生氏の所領は六万石と言われている。これは、実際にその所領を書き出したものや、具体的な宛行状を根拠とした数字というわけではなく、天正十二年に氏郷が伊勢南郡一二万石を領することになった際、「日野六万石ノ知ニ倍シテ」と『蒲生軍記』に記されていることに起因すると考えられる。それにしても六万という数字は、所領が倍になったという物語を構築するために創作された意図も多分にふくまれよう」。
ほ:ということは、確たる根拠のある数字ではなく推測も含まれているのですね。
悦:もう少しこの話を続けますよ。1570年、大河内城攻めの翌年、織田信長は越前朝倉を攻めますが、これは失敗し、這々の体で京に戻り、そのあと居城の岐阜に引き上げるとき、千種越えをします。このルートを準備したのが蒲生賢秀です。
ほ:千種越えは、三重県の菰野町に抜けるルートですね。杉谷善住坊による信長狙撃事件があったことで有名です。
悦:善住坊の失敗は、「ゴルゴ13」でも出ましたね。
ほ:信長の銃撃に失敗して無惨な末路をたどった善住坊の子孫がゴルゴ13に復讐を依頼するというお話でした。杉谷善住坊は井沢元彦さんの小説にもなっているみたいです。
悦:この直前の元亀元(1570)年5月15日に、賢秀、氏郷宛に現在の所領の安堵と、小倉氏の旧領2千石を含む5510石の領地を宛行う朱印状が与えられています。これは具体的な数字ですね。さらに本能寺の変、そして信長の家族をかくまった日野籠城の後ですが、「明智に味方した者の領地は皆取り上げられた。その時秀吉は蒲生家へ三千石を加増した」と書く本(『蒲生氏郷小伝』山田勘蔵)もあります。
先ほどの『近江日野の歴史』では、「仮に六万石だったとしても、この安堵状(前回紹介した清洲会議の時のものです)で得たような他郡の所領も含めた、近江時代最終の石高だったと思われる」と書いています。つまり近江日野の所領に、功績を挙げるたびに加増された分もみんな合わせて6万石位だったんじゃないか、ということです。このように流動的で不確かな数が横行する中で、松ヶ島に移って、やっと所領の石高の細かい数字が出てきます。12万3155石です。
ほ:この後の「羽柴筑前守秀吉知行割之事」に出る数字ですね。「飛騨守自分与力、合拾弐万三千百五十五石」。
悦:そこで「倍だ」と書かれたら、二分の一が日野時代の所領だろうとなるわけです。それと、よく見て下さい。「飛騨守自分与力」とあります。飛騨守氏郷の自分の分と、「与力」つまり加勢してくれる人の分を合わせた数なのです。また、旗下に入った、つまり加勢してくれる田丸直昌、関一政、大和国宇陀の沢、秋山、芳野の知行三万石を合わせると実高は15万石だとか、検地をしたら石高が増えたとか、実にややこしいですね。
ほ:そう考えると、信長、秀吉の天下統一は、国の秩序を明確にするという意味で、だいじなことだったんですね。
悦:次の「小田原の軍功」というのは、秀吉が北条氏直の小田原城を攻めた時ですが、その功績で会津42万石、1591(天正19)年には91万9320石、ほぼ92万石ですね。これに検地で増えた分を合わせると百万石、これが氏郷の最終石高でしょうかね。
 氏郷まつりで市民が扮した氏郷公。
氏郷まつりで市民が扮した氏郷公。
鯰尾(なまずお)の兜を着用している
(写真提供:松阪観光協会)
ほ:その飛躍的に所領が拡大した「小田原の軍功」では、敵将の夜襲に対し、氏郷が近くの者の甲冑を借りて奮戦したエピソードなどもあります。
悦:そうですか。知らなかった。
ほ:ご存じないとは思えませんが…ま、そういうことに…。こんな話もあります。小田原攻めの陣中、蒲生氏郷と細川忠興が、高山右近のところに牛肉を食べに行ったそうで、『細川家御家譜』という文書に出てくるそうです。この3人仲良しだったんだ、そして牛肉好きだったんだ、と面白く思いました。味噌味で食べたのかな、塩味かな、とか、近江牛や松阪牛が有名になったのと何か関係あるのかな…など楽しく妄想しました。
悦:妙な話が好きですね。泉鏡花の「天守物語」というのはご存じですか。読んだことはなくとも板東玉三郎さんのならご存じでしょう。白鷺城天守閣の中に巣くう魔物の話です。
ほ:もちろん読みました。鏡花は大好きです。「亀姫様お持たせのこの首は、もし、この姫路の城の殿様の」ですね。玉三郎では「汁(つゆ)」が足りません。
悦:鏡花がお好きだったとは、いやいや怖くなってきましたが、勇気を奮い立てて…。この物語は汁のしたたる生首ですが、私の手元に山田勘蔵さんの『蒲生氏郷小伝』があります。
ほ:先ほども出てきましたね。
悦:この小冊子には、氏郷14歳の大河内城攻め、初陣の時に「父上ツ、敵の首を見参。」に始まり、越前朝倉義景攻めで、「首二つ信長の見参に入れると、信長は激賞して」など、生首のオンパレードです。そんな氏郷たちなら、調理せずとも・・・
ほ:生食ですか…なるほど、そうかもしれません。亀姫は御姉様に、若き氏郷は父や信長への手土産として生首を持って行ったと…。「天守物語」はファンタジーですが、氏郷の生きた中世は、そういう血なまぐさい時代だったのですね。現代の感覚では猟奇的ですけど。ちなみに、私は松阪肉のお刺身も大好きです。生姜醤油などでいただきますね。これは血なまぐささは皆無で、さわやかで上品なお味です。さて、この後、付箋や頭注の文章が付いていて、氏郷についての情報やエピソードがいろいろ出てきます。これを読んでいきましょう。「松阪市史」では「註②」として頭注と付箋4種が載せられていますが、ここでは便宜上、1~5の番号と付箋にはA~Dの記号を付けておきます。
悦:その前に一言。
ほ:何でしょう。おそらく一言じゃないですよね。
悦:この頭注や付箋は、『松坂権輿雑集』でも、宣長の手沢本、使っていた本に書き込まれています。
宣長にとっては、蒲生氏郷は重要な関心事だったのです。
ほ:本居家のご先祖様は国司・北畠家の家臣で、北畠が滅亡した後、氏郷に仕官したのでしたね。
悦:阿坂城、白米城ですね、そこの目付だった本居武連には二人の子がいました。北畠家が滅亡した後、兄・延連(のぶつら)は武士を捨て農業の道を選び、弟・武秀は蒲生氏郷の家臣となり、奥州を転戦します。
ほ:北畠という会社が倒産して、兄は田舎に帰りお百姓、弟はライバル企業に引き抜かれた、という感じですね。
悦:氏郷が会津に所替えとなったのは、伊達家をはじめとする奥州勢を抑えるためですが、秀吉が危惧した通り天正19(1791)年に南部の九戸政実(くのへ・まさざね)が反旗を翻します。制圧のために九戸へ攻め入る氏郷軍、その中で、哀れ本居武連は討ち死にするのです。
ほ:あっぱれ討ち死にではなく哀れ討ち死にですか。
悦:また話は横道に逸れます。「あわ(は)れ」と私は言いました。これは“気の毒に”の意味で使用しましたが、本来は悲しみでも喜びでも、心が揺れ動いたときに「ああ」と洩らす。それが「あはれ」の語源ですが、やがて「あはれ」が促音化し「あっぱれ」となった訳です。
ほ:本居宣長の「もののあわれを知る」説ですね。
悦:その通り。さて武連の妻・慶歩大姉は懐妊していました。身寄りのない奥州では不安だと、従者と伊勢国に戻り、松ヶ島の近く、小津村で子供を産みます。七右衛門道印です。その子は、長じて小津を名乗り、商人となる。その子孫が宣長です。だから北畠氏以上に蒲生氏のことは関心があったのですね。
ほ:宣長さんにとっては蒲生家の盛衰は人ごとではなかったのですね。では、その頭注から見て行きましょう。
1,頭注
「蒲生軍記」に曰く。氏郷、松ヶ島に封せられてより、爵禄いよいよ加はり、武名なお盛んなれば、我が家松の字を吉祥すと云て、四五百杜を改めて松坂と名つけらる云々。宣長按ずるに、会津の城地を若松と名付けられしも此の意なるへし。
ほ:この話は有名ですね。氏郷は松ヶ島に来てから幸運が続くので、「松」の字が自分にはラッキーだということで、四五百森を「松坂」にしたのだと。さらに宣長は、会津を「若松」と名付けたのも同じ理由だろうと言います。
悦:出典の『蒲生軍紀』というのは、先に出ましたが、蒲生家の戦記を纏めた読み物です。話の大半は、氏郷と信長の娘の祝言から逝去までと、氏郷の話が中心です。1695(元禄8)年以後、何回か出版されましたが、宣長がどの版を見たのかはわかりません。この本のもとになった『氏郷記』や、『蒲生氏郷記』など、よく似た本はいろいろ江戸時代に書かれています。
ほ:続いて2番目、付箋Aです。これは、氏郷の子どもの系図ですね。
2,付箋A

秀行の三子の母は、家康公の御女也。秀行逝去に因りて、元和二年(1616)、秀忠公の御養女として浅野但馬守長晟へ再嫁。光晟の母公也
ほ:蒲生秀行(1583‐1612)は氏郷の長男ですね。父は氏郷で、お母さんはどなたですか。
悦:織田信長の娘です。大河内城の合戦のあと、冬に姫を娶ったとあるので、「冬姫」ではと言われたりもしますが、よく分かりません。
ほ:信長の娘であっても、女性は名前もしられずに歴史の闇に消えていくのですね。
悦:「可愛い子供は女の生命」と申しますが、その秀行も早逝します。
ほ:秀行の妻は徳川家康の三女・振姫で、3人の子どもがあったのですが、秀行の没後、浅野長晟(ながあきら)に再嫁し、光晟が生まれています。
悦:浅野長晟はその後、和歌山城主となり、1619(元和元)年、安芸広島に転封、そのあとに徳川頼宣が入城しました。さて、次の付箋に蒲生氏の詳しい情報がありますので、そちらを見ましょう。
ほ:はい。次の付箋は少し長いので、2つに分けますね。
3,付箋B‐1
蒲生氏之事
明応(1493-1501)の頃蒲生貞秀入道知閑、武勇にして歌道にも志あり。其の子、左兵衛賢秀、其の子、忠三郎氏郷也。代々江州日野の牧・音羽城に住し足利氏に仕ふ。氏郷は信長公、秀吉公に仕へ、天正十二(1584)年、十万石加増にて勢州松坂へ移り、本知八万石共に十八万石と成り、同十八(1590)年、小田原戦功によりて会津六十万石を賜ひ、同十九年、九戸乱に功ありて百万石余となる。文禄四年(1595)二月七日逝去。四十歳也。
悦:まず氏郷のご先祖の話から始まりますが、ここは要注意です。「付箋」、つまり宣長の記述をそのまま読むと、祖父は蒲生貞秀で、武勇に優れ歌道にも通じていた、となりますね。
ほ:その子が賢秀で、氏郷とつながっていきますが、ここに問題があるのですか。
悦:実は、貞秀知閑は賢秀の曾祖父なのです。「貞秀知閑-高郷-定秀-賢秀-氏郷-秀行-忠郷」となります。
ほ:宣長が間違った? なんと珍しい。ひょっとしたら氏郷の祖父の定秀と、テイシュウ違いで貞秀とを取り違えたのかしら。
悦:二人とも「さだひで」ですから、可能性はなくもない。しかし、宣長が間違うということは考えにくいので、「其の子」は、その子孫の意味かも・・・
ほ: いかに“宣長ファースト”の吉田さんとしても、ちょっと苦しい解釈かと思いますが、同じ読みの名前で紛らわしいですし、書写した本に添えた付箋なのですから、間違いと言ってしまっては宣長さんが気の毒な気もしますね。
悦:貞秀は、常に念仏を唱え目を閉じて数珠を爪繰って脱俗を装いながら、頭の中は戦のことばかりだったそうです。根っからの武人なのですね。その一方で、宣長も書くように、歌人としても優れていて、連歌師・宗祇との交友も知られています。本居宣長記念館には、文明6(1474)年10月、近江の坂本、禅林坊で詠んだ「山王法楽」詠草や、宗祇添削の詠草が伝わっています。何れも、松阪市指定文化財です。


ほ:こんなにも昔の人の詠んだ歌を今もみることができるって素敵なことですね。遠い名前だけだった存在が、人として立ち上がってくるようです。さて、また付箋の解説に戻りましょう。ここに書かれているのは、貞秀知閑の曾孫・賢秀(1534‐1584)は、代々日野の牧・音羽城を居城として足利氏に仕えていた。その子が忠三郎氏郷で、信長や秀吉に仕え、もとの8万石に10万石加増して1585年に松坂に移り18万石となり、1590年、小田原の戦功で60万石、そして先ほど名前の出た九戸乱を平定し100万石となったということですね。細かい数字はともかくも、このあたりはほぼ本文と同じですね。
悦:「日野の牧」は、今の日野町一帯です。中世には日野のあたりにもいくつもの荘園がありましたが、その中で一番有名だったのが「日野の牧」でした。牧というのは牛馬を放牧する土地ですが、そこも時代の流れの中で、次第に開発されて耕地となっていきます。音羽城は蒲生氏の拠点ですね。
ほ:前に皆さんとバスで日野に行ったとき、見学しませんでしたっけ?そばに雉がいた池のあったところ。
悦:それは蒲生氏のもう一つの城で、現在の町の中心部に近いところにある中野城址ですね。音羽城が廃城になって築かれた城です。そこから少し南に離れたところに音羽城はありました。
ほ:百万石となったその氏郷ですが、1595年に40歳で亡くなります。若いですね。
悦:松ヶ島から松坂へ、相次ぐ合戦、会津若松城の築城、また京都の豊臣秀吉へのごあいさつと席の温まる暇もない。会津と京都の間を行ったり来たり、そこへ朝鮮出兵です。氏郷は、海は渡らなかったようですが、遠征先の九州で下血、発病しました。
ほ:毒殺説もありますね。
悦:辞世の歌とされる、「限りあれば 吹かねど 花は散るものを 心みじかき 春の山風」から毒殺だと言うのですが、いかがなものでしょうか。高名な医者・曲直瀬(まなせ)玄朔が診察し、『医学天正記』に病状の進行について詳しい記録を残しています。それを見る限り、病死でしょうね。朝鮮征伐のために赴いていた肥前の名護屋で発病。薬石効無く、1595(文禄4)年2月7日、京都で亡くなり、大徳寺塔頭昌林院(現、黄梅院)に葬られました。
ほ:歌に無念がにじみますね。では続けます。こちらは氏郷以後の蒲生家についてです。
3,付箋B‐2
子息・鶴千代丸その時十三歳。御母公は信長公の御女也。鶴千代元服して藤三郎秀隆と云い、後に秀行と改め飛騨守となる。四位侍従となる。秀吉公媒にて東照宮の御聟となる。其の内会津騒動の事ありて、秀行幼少の間は会津を召し上げられ、上野国宇都宮にて十八万石を賜ふ。秀吉公薨じたまひ、慶長六年(1601)八月に、再び会津に移り六十万石となる。同十七年(1612)五月十三日、病死、三十歳也。嫡子下野守忠郷相続す。松平を賜り、御諱の忠の字を賜ふ。疱瘡にて寛永四年(1627)正月四日早世、二十五歳なり。子息なくして領知召し上げらる。然れども、此の家断絶成され難く、舎弟・中務小輔忠知、伊与松山にて二十万石賜る。従四位下侍従也。同十一年(1634)八月十日病死、三十歳也。この時、内室懐胎也。出生たとひ女子なりとも相続すべく仰せ付けらる旨の上意あるところに女子出生、程なく早世す也。是によりて蒲生家断絶す。忠知の内室は、内藤左馬助某の長女也。正壽印殿と号す。元禄十三年(1700)六月六日八十五歳にて卒去あり。
ほ:息子の鶴千代が13歳の時、父・氏郷が亡くなります。母は織田信長の娘です。氏郷まつりの武者行列には正室の冬姫が登場しますが、名前についてはよく分からないということでしたね。氏郷は正妻以外に側室を持たなかったといわれています。愛妻家だったのかもしれませんし、父の信長の威光もあって重要人物だったのかもしれません。
悦:愛妻家と言うより戦にしか興味がなかったのでは・・
ほ:そして、鶴千代が元服して秀行となり、秀吉の媒酌で家康の娘を妻にしています。そこに3人の子どもがあるのは、前出の系図の通りです。秀行は、会津騒動でいったん18万石に減らされ上野国に移りますが、その後、60万石で会津に戻ります。でも30歳で病で亡くなり、その長男の忠郷も25歳で疱瘡で没します。子息がないため領地は没収されます。次男の忠知も伊予の國で20万石を受けていましたが30歳で病死。妻が懐妊していたので、女の子であっても家を継がせるということでしたが、女児が生まれてほどなく亡くなってしまい、蒲生家は絶えてしまいます。忠知の奥さんだけは長生きしたようですが、氏郷も二人の息子も短命でした。
悦:ここにある会津騒動というのは、氏郷亡き後、幼少の秀行を守り立てるはずの家老・蒲生郷安が、やはり重臣だった綿利良秋を殺すという事件です。秀吉も奥州の要衝・会津と蒲生家を守るためにいろいろ考え一時転封させたりするのですが、秀行も、その子の忠郷も、忠知も、その子までも亡くなってしまって、結局、蒲生家は滅んでしまいます。
 氏郷まつりでの冬姫
氏郷まつりでの冬姫
(写真提供:松阪観光協会)
ほ:次の付箋に移りましょう。これは宣長の写した本にだけある付箋のようですね。
悦:ここで一つお断り。付箋が続きますが、そもそもが補足説明や情報なので、行きつ戻りつして、本文の流れを妨げてしまいますね。それと、これは最初にお断りしておかないといけなかったのですが、付箋や書き込みは、漢字片仮名表記ですが、漢字平仮名に改めていますので、ご了解ください。
ほ:はい。前後関係を考えながら読まないと混乱しますね。次の付箋では氏郷の少年期に戻ります。
4,付箋C
[多気実記五]蒲生下野守入道快翰子息左京大夫賢秀は、日野の城にこもり、武威をふるひ云々……蒲生かたひでの子・鶴千代丸を人質に観音寺の城へ送り、信長に礼義を述べ給ふ。信長、一目見て、此の稚児眼ざし常ならぬ、必ず武芸有るべし。我が聟にすべしと約束せらる云々。明年、信長の九歳の息女を給はり、祝言相済む。後に鶴千代元服して蒲生忠三郎氏郷と名付け給ひけり。
悦:織田信長が足利義昭を伴って上洛するときに従わなかった南近江の六角氏、いったんは観音寺城(安土町・東近江市)に立て籠もりますが、迫る織田の軍勢におののき逃走。配下の武将や近在の武将たちも降参し、人質を差し出します。蒲生家の鶴千代もその一人です。
ほ:鶴千代が後の氏郷ですね。『多気実記』を読むと、小さい頃からただ者ではない気迫が漂っていたようです。人質に出されても堂々として、娘婿にしたいほど有望な少年だったのですね。この『多気実記』ってやはり軍記物ですか。
悦:この本については、知りません。書名は、北畠氏の話なら「たき」ではなく「たげ」と読むのかなと思う程度です。
ほ:ご存じないと…?冷淡なんだから、もう…。次に進みましょう。次の付箋も2つに分けます。
5,付箋D-1
『蒲生記』に云う。天正十六年戊子(1588)春の頃、関白殿西京に御在城を建てたまひて、聚楽城と名付けられ、其の額、江州建部傳内助之を書く。めでたかりし御城なり。同四月十四日、主上、新造の御所聚楽城へ行幸なる。そのとき、主上、叡感のあまりに、関白殿以下の諸大名に除目行はれしに、氏郷朝臣は正四位下左近衛少将に任ぜられけり。
ほ:聚楽第で天皇から位をもらった話です。除目って平安貴族のイメージですが、武士に対しても行っていたのですね。しかも臨時で――。氏郷は正四位ですね。
悦:この聚楽第行幸は、一大イベントでした。その様子は『聚楽第行幸記』(『群書類従』帝王部)に載っていますが、公卿、大名など夥しい人が動員されました。
ほ:氏郷もその一人ですね。
悦:「松加島侍従氏郷朝臣」とか「松嶋侍従豊臣氏郷」として出てきます。また「松かしま侍従豊臣氏郷」で歌も詠んでいます。
ほ:「松坂」ではなく「松ヶ島」、蒲生でなく「豊臣」なのですね。
悦:このイベントは後陽成天皇と公家衆の所領を安堵し、また天皇の権威で諸大名に秀吉への忠誠を誓う起請文を提出させて、伝統的な官位体制のなかに位置づける意味を持っていたのですね。この時に多くの大名が豊臣姓を許されたのです。
ほ:これは天正16(1588)年のこと。松坂開府の年ですね。
悦:そうです。ただ氏郷が松坂城に入るのは8月なので、この時点では「松ヶ島」ですね。それと、聚楽第の扁額を書いた建部氏は、やはり近江佐佐木家に仕えた武将ですが、建部氏からは能書家も出ているようですが、まだ詳しくは調べていません。
ほ:では、付箋の続きです。
5,付箋D-2
同年秋の頃、氏郷朝臣も松島の在城を四五百の森へ移されけり。此所、もとは大力の覚えとりし伊勢国の住人潮田が城なりけり。在所は、誠に小さけれども、地形を広め、船江へ続けたらんに於いては、栄ゆべき所也と、氏郷自身目明ありて移されける。氏郷朝臣、松ヶ島に在城ありしより一段と仕合わせよく、初月の宵々に光を増させ玉ふがごとくなられしかは、兎に角、我には、松の字吉相なりとて此の四五百森を改めて松坂と名つけられけり。漸々普請も出来せしかは、実に松の若緑の春を待ち得て生ずるがごとく、日々に増って繁り昌へけり。爰に種村大蔵入道慮斎は、本は信長公に事へて、お咄の衆にて候しが、今氏郷之家に事へても同じく咄の衆にてぞありける。今度家中の面々松坂にて屋敷を取り、美々敷き家を建てしに、慮斎が庭には富士山を築きたりと聞こえしかば、或る時氏郷、去らば御辺が庭を見むとてわさわさ参られしに、かの築山を見たまへば、頂き丸き山なり。氏郷は一年信長公武田退治のとき東国下向ありて富士山一見あれば、こはいかに、かかる富士山は聞きも及ばずと笑ひ興ぜられて、硯、料紙を乞ひ出され、一首の短冊を詠みて此の築山に立てそ戻られける。
富士見ぬか富士には似ぬぞ松坂の慮斎が庭の摺り子木が嶽
氏郷朝臣松坂へ在城を遷され後は、世の人松坂の少将とぞ申しける。
ほ:ここも、氏郷が松ヶ島城を四五百森に移して松坂と名付けた話です。小さい場所だけれど、船江に続けたら発展するに違いないという氏郷の目算のほか、潮田のことや「松」が吉祥なことなどが述べられています。
悦:月が日を追って明るさを増すように、松ヶ島に来てから氏郷の運気はいや増しに増したので、「松は吉祥の字だ」となったのですね。
ほ:ここでは、種村慮斎という信長から氏郷に仕官先を変えた“お噺の衆”が出てきます。氏郷が居城を移したのに従って、家中の武士たちも松坂にそれぞれ立派な家を建てたのですが、その中で、慮斎は庭に富士山を築いたと聞き、氏郷がわざわざ出かけたところ、その築山は頭が丸かった。氏郷は富士山を見たことがあったので、こんな富士山は聞いたことがないと笑って「慮斎が庭のすりこ木が嶽」と短冊に書いて戦国ジョークを発しています。お噺衆には博学多識で豊富な体験が要求されたということですが、氏郷の方が博識だったということですね。それに案外洒落のきいた武将ですね。
悦:松坂時代の氏郷がはたして富士山を見たことがあったのか、疑問ですがね。
ほ:冷淡を超えて棘があります…。まぁ、美化してる感じは否めませんけどね。さて、氏郷について「権輿雑集」にあるのは以上ですが、これ以外では、レオンという洗礼名を持つキリシタン大名だったことが挙げられると思います。肉食仲間の高山右近もキリシタン大名ですから、肉食については宣教師たちの影響が考えられます。そういえば、勢州松坂会の駒田満さんが、松ヶ島にある「テレン」という地名は「バテレン」からきているのではないかという考察をされていましたね。
悦:面白い話です。そうかもしれない…と思ってしまう。でも、町名については、織田信雄も宣教師と親しくしていましたし、そのあたりは慎重に考えないといけませんね。松ヶ島については、またじっくり考える機会を持ちましょう。
ほ:はい。それから、千利休に「文武両道の御大将」と讃えられ、利休七哲にも加えられている茶人であることも挙げられますね。石水博物館で、利休作の「音曲」という竹一重切花入を見たことがありますが、これには羽柴忠三郎の略「羽忠」の記名がありました。秀吉から羽柴姓をもらっていた氏郷の名前ですね。力強い書体で、エネルギーを感じました。
悦:先の「小田原の軍功」の時、秀吉にしたがった利休が韮山の竹で作った竹花入は三つあります。「園城寺」、「尺八」、そして「音曲」ですね。『石水博物館名品図録』にも写真が載っています。それとは別に、背の「羽忠」が映る写真を見ましたが、その下に「休」の文字もありますよ。それはともかく、この竹花入のおなり、つまり形が美しい。やや歪みがある錆竹ですが、この歪み、少しなよやかなフォルムが、すっくと立つ一重切花入に比べて軟らかくて素晴らしいですね。氏郷の竹茶杓も、東京国立博物館所蔵のものは力強く剛胆ですが、本居宣長記念館のはすらりとしていて、ともすれば力強さに欠けると言われたりもしますが、こんな一面を氏郷は持っていたのかもしれません。
ほ:ああ、なるほど。あれは氏郷の署名ではなく、羽忠にあげますよ、という利休の書なのですね。「羽忠」の文字に引き込まれて「休」に思い至りませんでした。それにしても、ここに至って、ようやく氏郷に対して好意的な見解を出されましたね。吉田さんもお茶をなさってるから、お道具を通してみると違う側面が浮かびあがるのかもしれません。氏郷は、関や亀山あたりでは「ガモジが来るぞ」とやんちゃな子供を脅かしたという話もあるように、怖い武人のイメージが強いのですが、存外、この花入や茶杓のような優美を好む一面を秘めていたのかもしれません。鯰尾の兜などではエッジの利いたセンスも見せて独特な審美眼をうかがわせますし、短い生涯を多彩に生きた武将として、私は魅力を感じます。では今回は以上としまして、次回は秀吉からの知行割についてです。
『松坂権輿雑集』を読んでみた|2025.06.1
前 本居宣長記念館 館長
國學院大学在学中からの宣長研究は45年に及ぶ
『本居宣長の不思議』(本居宣長記念館) 『宣長にまねぶ』(致知出版社)など著書多数
編集者 三重県の文化誌「伊勢人」編集部を経てフリーランスに
平成24年より神宮司庁の広報誌「瑞垣」等の編集に関わる
令和4年発行『伊勢の国魂を求めて旅した人々』(岡野弘彦著 人間社)他 編集