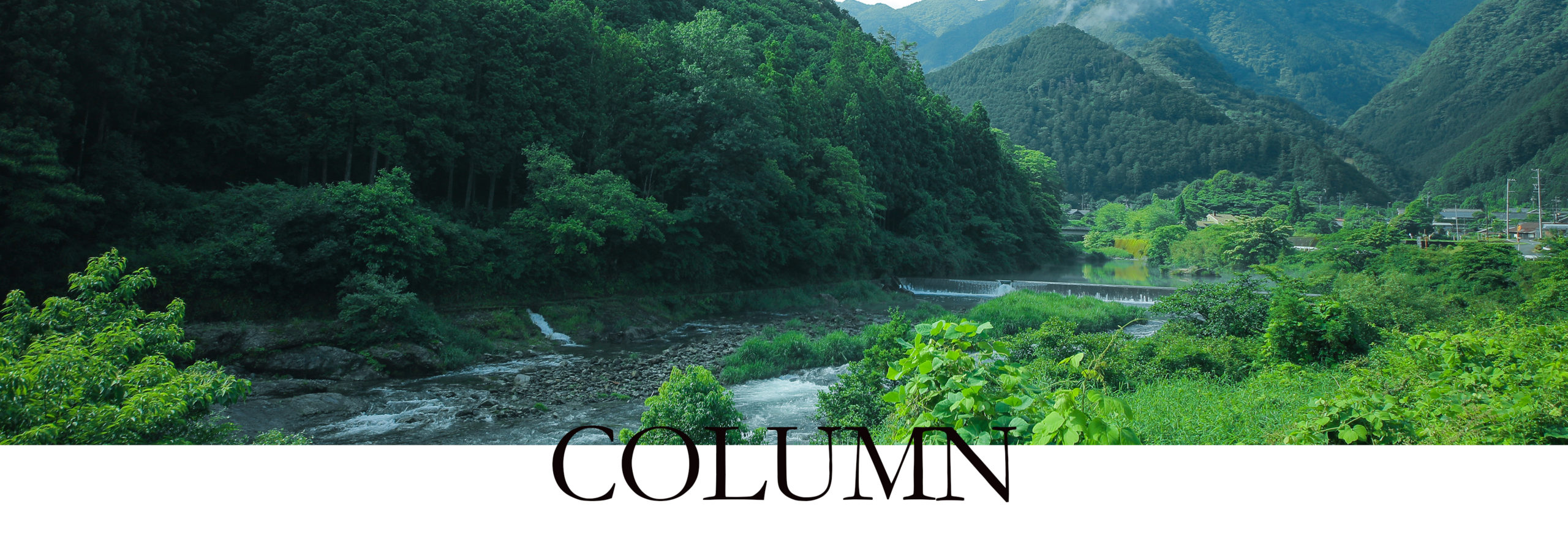
悦:吉田悦之 ほ:堀口裕世
ほ:今回は「羽柴筑前守秀吉知行割之事」です。これは、この地域の石高の分配についての通達ですよね。巻末に、「天正十二年【甲申】年九月、筑前守、秀吉、朱印」とあります。秀吉の朱印状ですね。
悦:織田信長が本能寺で亡くなって2年後に出された、秀吉の家臣への知行割ですね。南葵文庫本には「蒲生飛騨守知行割之事」とあるように、目録の大半は氏郷領です。「石高(こくだか)」は、その土地の生産能力を米の収穫量に換算したものです。この「知行割之事」でかなり具体的な数字が出てきましたね。
ほ:知行割とか、前回に見せていただいた安堵状って、とてもスピーディーに出されるのですね。
悦:先手必勝。まず手を打っておくということでしょうか。話が長くなり恐縮ですが、この前後の時代の流れをご説明しておきますね。まず1582年6月、本能寺の変で織田信長が討たれました。弔い合戦で勝利したのは羽柴秀吉で、清洲会議で信長の孫・三法師(2歳)の後見人となりました。信長の子で北畠に養子に入った信雄も秀吉の側に付きますが、柴田勝家や織田信孝等はそれに反撥します。信孝に味方をした滝川一益は北伊勢を本領としていましたが、やがて柴田勝家が賤ヶ岳の戦いで敗北。信孝も自害、一益も降伏します。実質、信長の後継者となった秀吉に対し織田信雄は徳川家康と同盟を結び、小牧・長久手の戦いとなります。
ほ:目まぐるしく状況が変わるのですね。
悦:小牧山の戦いは持久戦となり、羽柴秀次が岡崎攻めをするも長久手の戦いで大敗。一方、伊勢方面で羽柴秀吉軍と戦っていた織田信雄は、勝手に和議を結んで、ひとまず戦は終わります。そして信雄から取り上げた南伊勢地方を、秀吉は合戦の功労者に分け与えたのです。実際、両者の和議が整ったのは11月12日ですが、既に南伊勢割譲はほぼ決まっていたのでしょう、信雄も9月10日に家臣の知行替を行いますが主に北伊勢、尾張国で、秀吉の知行割とは、ぶつかってはいませんね。
ほ:ここには一志、飯高、飯野、多気、度会の五郡が出てきます。これが南伊勢ですね。そして各郡の石高が示されます。まだこのあたりの検地は行われていませんね。
悦:そうですね。注目すべきは「石高」での表示ですね。土地の価値を表すのに、それまでは銭価で表す「貫高制」で、織田信雄領も貫高制だったのが、石高で表す。支配者の交替がこのようなところにも顕れてきますね。
ほ:ほ~、石高で表すようになったのは新機軸だったのですね。一志郡は今の松阪市と津市、飯高郡は松阪市、飯野郡は松阪市と多気郡。多気郡は多気郡。渡会は度会郡と伊勢市でしょうか。
悦:手元にある『角川日本地名大辞典 三重県』見返しの「三重県行政区画変遷要図」の一部をお借りしましたので、これで概要を把握して下さい。
ほ:明治時代でもまだ津、松阪、伊勢という分けかたではないのですね。この「郡」というのはいつから出来たのですか。

悦:わかりません。『倭名類聚抄』という本があります。「和名抄」とも言います。承平年間というから930年頃、源順(みなもとのしたごう)が編纂した百科全書です。
ほ:平安時代ですね。
悦:これが役に立つんだなあ。宣長も『古事記伝』でバンバン使っています。この中に、陸奥国から薩摩国、壱岐、対馬まで、つまり北海道と沖縄を除く日本全国の郡名が記されています。たとえば、写真は宣長が使っていた本の該当部分です。
悦:伊勢国一志郡を見ると、そこには八太、日置、島抜、民太、神戸、須可、小川、呉部、宕野、それと余戸がある。飯野郡は乳熊、兄国、黒田、長田、漕代、神戸、飯高郡は上枚、下枚、丹生、立野、駅家、神戸などとありますね。
ほ:一志郡の上の余白に何か書いてありますね。「阿坂ノ観音ノ山号ヲ呉部山ト云ヨシ」。
悦:マルジナリア、宣長の書入れです。内容はちょっと面白いのですが、話が横道にそれるので、省略。堀口さんは度会郡なら詳しいでしょう、宇治、田部、城田、湯田、伊蘇、高田、箕曲、沼木、継橋、二見、伊気、駅家、陽田が書かれています。
 『倭名類聚抄』本居宣長手沢本(本居宣長記念館蔵)
『倭名類聚抄』本居宣長手沢本(本居宣長記念館蔵)ほ:あら、脇道に入らないのですね…。それにしても郡はずいぶん古くからあったのですね。宇治とか二見は分かりますし、伊蘇は磯かしら、陽田は山田(ようだ)ですね。何となくわかるところもあります。
悦:この地名が、現在のどこにあたるのかという比定は、昔から一つの研究テーマですが、ともかく現在の津市、松阪市、多気郡、度(渡)会郡、伊勢市一円ですね。その中の一部を、秀吉が配下に分割した記録ということです。
ほ:郡も村も、その土地の支配者もまだ固まっていないのですね。
悦:飯高の水屋神社近く、櫛田川の中にある「礫石」はご存じですか。
ほ:むかし、伊勢の神さまと大和の春日の神さまが国境を決めるのに投げ込んだ石だという伝説がありますね。深い緑の中を静かに流れる櫛田川の中ほどにある、形のよい石ですね。
悦:写真があるのでみて下さい。和歌山街道の珍峠の切り通しの所から川に下りたら見えますね。その対岸に素晴らしい楠がある水屋神社があります。
 礫石
礫石ほ:この楠木は確か県の天然記念物ですよね。
悦:この神社の記録に、驚くようなことが書かれています。慶長5(1600)年、「松坂城主古田重勝家老小池文左衛門に命じ田引より舟戸までの寺社の棟札に大和州の記あるものを焼却せしめる」(『飯高町郷土誌』837頁)。この焼く前に記録したのでしょうか、水屋神社の棟札には、文中2(1373)年の年号と「大和州閼伽桶庄宮」とあったそうです。
ほ:大和じゃなくって伊勢ってことにしてしまおうと…古田重勝、強引ですね。「閼伽桶(あかおけ)」は、今の飯高町赤桶(あこう)ですね。
悦:ちょっと珍しい地名ですが、仏様にお供えするものを「あか(閼伽)」と言います。今は伝わっていませんが、なにかそんな伝説があったのかもしれません。
ほ:水屋神社は奈良の春日大社にお水送りをすると聞きました。大和とのかかわりが強いようですね。飯高郡は現在の県境・高見峠までではなかったのですか。
悦:この時期には、高見峠のあたりまでが飯高郡として間違いはないのですが、少し古い本で恐縮ですが岩波書店の『日本史年表』(歴史学研究会編)の1069年8月に「平維盛、大和河俣山の賊を討伐する」とあります。出典は『太神宮諸雑事記』で、「河俣山追討使等差遣て、伊賀、伊勢、志摩、大和、紀伊国等の要害等問はしめて」とあります。奥深い山が続いているのだから郡や村どころか国境だって曖昧だったのでしょう。それが、このように石高を示すことで、支配が明確となり、村や郡、そして国の境界線もはっきりしてきたのですね。
ほ:このあと行われる「検地」で土地の境界が示されたわけですね。
悦:言葉の問題はありますが、統一国家が出来て、境界線や支配体系も整うということですね。と言っても、私は素人だから話半分で聞いておいて下さい。
ほ:では、本文を読んでいきましょう。便宜上、項目ごとに数字や記号を振っておきます。
羽柴筑前守秀吉知行割之事
知行割目録
① 一、壱志郡高
六万二千八百六十六石八斗六升之内北に付ける
ア 三万石 民部少輔殿自分
イ 三千石 榊原
ウ 二千八百石 藤方
エ 五百石 長野左京
オ 五百石 水谷
カ 三千石 河北左助
キ 二百石 無軍役 垣川次助
ク 合四万石
ケ 松ヶ嶋廻より たげ谷まで北に付る、算用次第
A 二万二千八百六拾六石八斗六升 蒲生飛騨守
ほ:先ほど説明されたように、時代の覇者・秀吉が自分の配下に分配した所領の石高です。
悦:この「知行割」や、次の「町中掟」など、松坂の歴史を語る上での根本資料です。このような大切な記録をよくぞ残してくれたものと著者の久世兼由に感謝します。
ほ:ケは「松ヶ島廻りより、多気谷まで、北は境界線まで」ということでしょうか。現在の松阪市松ヶ島町あたりから西は多気、北畠の居城があった上多気、今の津市美杉村あたりのことになります。「北に附ける」は安濃郡との境ということでしょうか。
悦:でしょうね。
ほ:「民部少輔殿」とはどういう人物でしょうか。「自分」は自らの分?
悦:民部少輔ご自身の取り分ということです。民部少輔は、信長の弟・織田信包(のぶかた)でしょう。安濃津15万石を領して「津侍従」と呼ばれています。秀吉方について柴田勝家、滝川一益攻略に功績があったので、それまでと同じ安濃郡をもらったのですが、その後、小田原攻めで秀吉の勘気に触れ改易となります。ところがその後、御伽衆になったりして、再び召し抱えられるという、何しろ忙しい人生を送った人です。
ほ:「算用次第」ってどういう意味でしょう?
悦:だいたいの数字は示したが、石高は実際の出来高によるということでしょうか。これもよく分かりません。
ほ:なかなか難しいですね。
悦:つまり一志郡の62,866石8斗6升の内からまず分配責任者の織田信包が3万石を取り、次に味方をしてくれた榊原や藤方など地元の武将に1万石を分割、残り22,866石を領主となる氏郷の取り分としたわけですね。
② 一、飯高郡
B 二万八千百五拾九石六斗 飛騨守
ほ:これは飯高郡だから、現在の松阪市街地周辺から飯南、飯高までですね。
悦:全部氏郷の所領でスッキリしています。
③ 一、飯野郡
一万六千三百二拾石三斗八升
④ 一、多気郡
二万四千百八石二升
③+④ 〇飯野多気両郡
合四万四百二拾八石四斗之内
C 三万四百二拾八石四斗 飛騨守
コ 〇御蔵入 一万石
サ 此の内千石 上部越中
ほ:これは飯野郡と多気郡ですね。併せて40.428石4斗の内、30.428石4斗が氏郷の取り分。残り1万石は御蔵入とあるのは、豊臣家の公の分と言うことですか。
悦:きっとそうでしょうね。その中から1000石を上部越中に下し置くわけですね。一志郡の所であったように、たとえば榊原氏に3000石、という分配とは違いますね。家臣団以外へ豊臣家からのお手当でしょうか。
ほ:上部越中に与えるとありますが、私、この人のことはちょっと知っています。この上部越中守というのは外宮の御師で、織田家や豊臣家などを檀家としていましたが、この人のご子孫が今も神宮で神主さんをされているのです。神宮には、この方以外にも古くから続く神主さんや御師のお家柄の方がおられます。でも、上部越中が知行を得ているのは意外でした。
悦:この頃の御師は、僧兵とはいわないけれど、戦に同行して、出陣の前に祈祷を行ったりもする。あるいは勧進や連歌師のように比較的自由に移動できるので、交渉や諜報活動なども行います。
ほ:神職のほか武士みたいなこともして、ネゴシエーターやスパイ活動もしたのですね。御師というと、世知にたけた如才ないエージェントというイメージが強いですが、これは江戸後期の姿で、武士だけでなく御師も、江戸時代以前はかなり荒々しい部分もあるのですね。ここに出てくる上部越中守は享禄2(1529)年生まれの貞永という人です。神宮の主事で神宮文庫に勤務してらっしゃる窪寺恭秀さんのご著書『伊勢御師と宇治山田の学問』を見ますと、貞永は、信長や秀吉から遷宮奉行や伊勢山田の奉行に任じられるなど、大活躍なんですね。神宮への寄進や、戦の時に兵糧米や竹材木の調達を命じたものなど、秀吉から上部越中守への書状もいろいろ残っているようです。
悦:『三重県史』(資料編・近世1)に載っていますね。上部越中守は秀吉の奉行人として町野重仍と神宮領を支配します。御師かと軽く考えてはいけません。なお上部氏は、このあとも出てきます。
ほ:いえいえ、軽くなんて考えてませんよ。御師は伊勢国だけでなく、全国的にみても大きな働きをしたと思っています。それにしてもこの上部越中守は驚きでした。
⑤ 一、渡会郡
二万八千七百石九斗七升之内
D 三千七百石九斗七升 飛騨守
E 〇飛騨守自分
合八万五千百五拾五石八斗三升
シ 一万五千石 田丸
ス 一万石 九鬼
⑥ 都合拾六万五拾五石八斗五升
セ 一、八千石 関 本知分
河曲郡神戸之内を以
ソ 一、二千石 同 新知
セ+ソ 合一万石
ほ:渡(度)会郡は結構広そうですが、28,700石9斗7升は少ない感じがしますが、神宮領もあるからかしら。
悦:きっとそうでしょうね。田丸氏、九鬼氏、関氏は在地の領主ですね。関氏は本知分と新地分とあります。河曲郡神戸に領していた分は安堵されて、新たに2,000石もらったわけですね。
タ 大和宇陀郡一円に飛騨守に遣わす内
一万三千石 澤、秋山、芳野
F 飛騨守自分与力
合十二万三千百五十五石
以上 筑前守 秀吉 朱印
天正十二(1583)甲申年九月
悦:先ほどは大和国と伊勢国の国境について分からないと言いましたが、今度は大和国の宇陀郡です。
ここには北畠氏の時代から宇陀を支配していた三家が、そのまま氏郷の勢力下に収まっていきます。
ほ:私、数字の流れがよく分からなかったので、この数字を電卓いれてみました。今までのお話といくらか重複しますが、数字のあらましについてお話させてください。大雑把にでも石高の概要を把握したいので。
悦:計算したのですか。まぁ、いいでしょう。
ほ:私もまさか氏郷の知行割を計算する日が来るとは思いませんでした。石、斗などの単位がよく分かりませんでしたが、普通に十進法で計算しました。
悦:氏郷の知行割ではなく、秀吉の知行割ですから、みんなが氏郷のものではないですね。
ほ:あ、はい。秀吉が出したものでしたね。まず①の62,866石8斗6升は一志郡から出る石高ですね。ア~キの合計がク・4万石で、これは氏郷とは無関係。①からクを引いたのが氏郷の一志郡での取り分で、A・22,866石8斗6升です。②は飯高郡の石高で、B・28,159石6斗。これはすべて氏郷の取り分です。③は飯野郡の石高・16,320石3斗8升。④は多気郡の石高・24,108石2升、③と④の合計は40,428石4斗となり、このうち、C・30,428石4斗が氏郷の取り分、コ・1万石は御蔵入、その中のサ・1,000石が上部越中に行きます。⑤は渡(度)会郡の石高・28,700石9斗7升で、そのうちD・3,700石9斗7升が氏郷分です。ここまでを合算するとA+B+C+Dで、Eの85,155石8斗3升です。渡会郡の残り シ・15,000石は田丸氏、ス・1万石は九鬼氏に行きます。
そして、⑥はここまでの5つの郡からの総額で、160,055石8斗5升と書かれていますが、
私の計算では①+②+③+④+⑤=160,155石8斗3升となりました。少し数字に差異がありますが、これは書き間違いかな…書写を重ねているのですからね。ここまでは大丈夫でしょうか?
悦:そうですね。合っていると思います。
ほ:この後が分らないんですよ。セの8.000石は、関氏のもともとの知行分、それに加増されたのがソの2,000石で合計が1万石。タは大和宇陀郡における氏郷の取り分から、澤、秋山、芳野氏が合わせて13,000石取ります。そして、Fの123,155石は氏郷の知行の総額ということでしょう。すると、氏郷の取り分のうち、FからEを引いた38,000石くらいがここには書かれていないことになります。大和や宇陀での澤達に分けた後の取り分か、①~⑤のほかにあった氏郷の本知分なのかは分かりませんが…。表にするとこんな感じです。
| 郡名 | 郡の石高 | 氏郷の取り分 | 氏郷以外に渡す分 |
|---|---|---|---|
| 一志郡 | ①62,866石8斗6升 | A 22,866石8斗6升 | ア~ケ 榊原等に40,000石 |
| 飯高郡 | ②28,159石6斗 | B 28,159石6斗 | - |
| 飯野郡・多気郡 | ③ +④ 40,428石4斗 | C 30,428石4斗 | コ 御蔵入10,000石 サ <内上部に1,000石> |
| 度会郡 | ⑤ 28,700石9斗7升 | D 3,700石9斗7升 | シス 田丸・九鬼25,000石 |
| 小計 | ⑥160,055石8斗5升 (160,155石8斗3升) |
E 85,155石8斗3升 | (75,000石) |
| 河曲郡
大和宇陀郡一円 |
記載なし
同 |
どこかの場所で 38,000石くらい? |
セソ 関10,000石 タ 澤等に13,000石 |
| 合計 | F 123,155石 | (98,000石) |
ほ:( )内は、本文にはなくて私が計算した数字で、青文字は推測です。このFが、松ヶ島城に入ったときの氏郷の知行と考えていいですか。
悦:そういうことになりますね。
ほ:イの長野左京については、少し情報がありましたね。長野左京亮と「亮」の字がつくようです。天文13(1544)年生れで、曾我兄弟に殺された工藤祐経の子。北畠家の侍大将として、永禄12(1569)年の伊勢攻めの際には日置大膳亮らと大河内城に籠城したのだけど、北畠と信長の和睦後は信長に仕えました。天正4年(1576)に信雄の命を受けて、他の侍とともに北畠具教が隠居していた三瀬館を訪れ、旧主・北畠具教を討ち取った、三瀬の変の渦中の人です。その後も、天正12(1584)年に秀吉と信雄が戦った戸木の戦いで、はじめは信雄方の木造氏に味方し、途中で豊臣方に寝返って、同じ長野氏の一族に討たれたとありました。
悦:そうですか。
ほ:長野のことをなんて節操のない裏切り者だろうかと思いましたが、ある本を読んでいたら、江戸時代以前の武士は「返り忠」といって、仕えている殿さまに見切りをつけて主君を乗り換えていくのが普通だったとあって納得しました。
悦:有能な主君に鞍替えするのは津の藤堂高虎がまさにそうだし、また主家が滅んでその敵方に仕官するというのは、既にお話ししましたが本居家もそうですね。長野氏の場合は極端な気がします。また確かに「返り忠」という言葉はありますが、決して称賛されるものではない。多少状況は違いますが、森鴎外の「大塩平八郎」に、「返忠を真の忠誠だと看ることは生まれ附いた人間の感情が許さない」とありますね。
ほ:江戸時代に「夫婦は二世、主従は三世」と、徳川家が儒教を利用した思想で統制したのが今に及んでいるのだと感じます。二君に仕えないのが武士の道で正義だという思想を刷り込むことで幕府の安泰を図ったのでしょう。それがいまだに私にもしみ込んでいるのだなぁとわかりました。考えてみれば、戦国時代は「うちの殿はだめだな」と思ったらさっと身をひるがえさないと生きられなかった厳しい時代だったのですから、仕方なかったのでしょう。御師もそうですが、同じ武士といっても、戦国時代と江戸時代の後半とでは全く思想が違うのですね。ほかの榊原、藤方、水谷等はどんな人か分かっていますか?
悦: 多少は分かっていますが、「お家がだんだん遠くなる」で、本筋から離れていくので、省略します。ただ、津市一志町小山に青巌寺という浄土宗真宗高田派の立派なお寺があります。少し高台にあり、平野を一望できる景勝の地です。
 青巌寺の山門からは伊勢平野を眺める
青巌寺の山門からは伊勢平野を眺める悦:ここは、もとは北畠氏の祈願所。主家滅亡の時、宇陀の秋山氏や沢氏は、北畠具親の嫡男をこの寺に入れました。三世明連上人(1596寂)です。その後も秋山、沢氏を始め具親の旧臣の多くがこの寺の塔頭の住職、また有力檀越となり、今も北畠血統の寺として続いています。
ほ:宇陀は奈良県ですが、三重県内の地域とのつながりも深いのですね。
悦:この「知行割之事」は、本能寺の変後、混乱状態に陥った南伊勢が漸く落ち着きを取り戻す様子を如実に記すものです。南葵文庫本には「蒲生飛騨守知行割之事」とあると言いましたが、氏郷以外の所領配分も述べられているので、この史料名は、必ずしも適切とは言えません。しかし、氏郷が中心人物だったのは間違いないところです。なお説明で省略した伊勢国大混乱の様子は『三重県史』通史編・近世1に述べられていますから、ぜひご一読ください。
ほ:はい…できたら読みたいと思います…。さて、これで秀吉からの知行割についての章を読み終えました。日々が戦いで、生き馬の目を抜く世知辛い時代の中で、知行を与えられる意味は大きいものだったのでしょう。宗教観も世界観も、あらゆる価値観が今とも、江戸時代とも、違うことが感じられました。次は、「蒲生飛騨守氏郷町中掟之事」です。ここも、“開けてびっくり”みたいな章ですね。楽しみです。
『松坂権輿雑集』を読んでみた|2025.07.1
前 本居宣長記念館 館長
國學院大学在学中からの宣長研究は45年に及ぶ
『本居宣長の不思議』(本居宣長記念館) 『宣長にまねぶ』(致知出版社)など著書多数
編集者 三重県の文化誌「伊勢人」編集部を経てフリーランスに
平成24年より神宮司庁の広報誌「瑞垣」等の編集に関わる
令和4年発行『伊勢の国魂を求めて旅した人々』(岡野弘彦著 人間社)他 編集