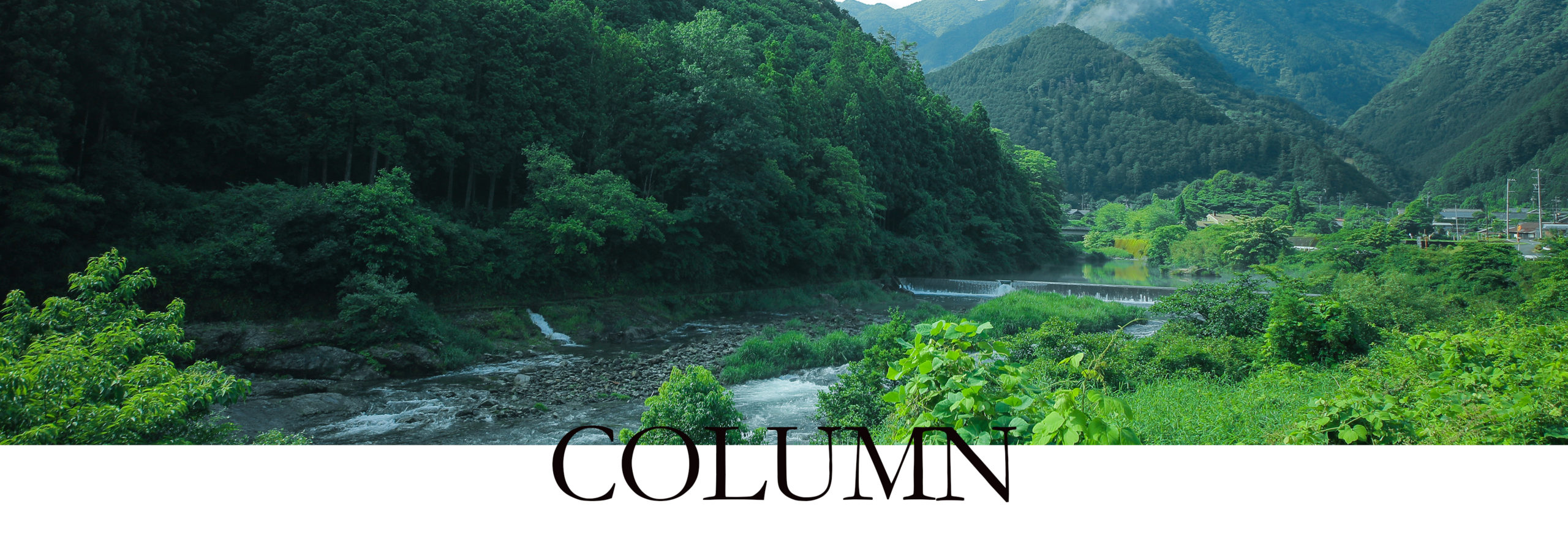
 「美濃田の大仏」
「美濃田の大仏」大仏殿は木造重層。上層屋根は四重造桟瓦葺、下層は本瓦葺。外部は朱塗り、連子窓に緑青を塗る。三軒田舎風であるが大仏殿を模す。
 「大仏殿(側面)」
「大仏殿(側面)」
大仏殿正面には「安養殿」と書かれた額がかかる。額には「安養殿、寛政漆(七)乙卯季十月吉菟山人普済誌書【金剛仏子】【慈観済印】」と書かれている。
 「安養殿の扁額」
「安養殿の扁額」
見逃してならないのは、この額の下である。
額を見上げていた私の隣で、隣にいた大西さんが、「ネズミがいる!」と叫んだ。
本物のネズミが走っているのかと驚き、指さす方を眺めると、木彫のネズミ。しっぽが長いとてもリアルなネズミが走っている。ぜひお見逃しなく

「大仏殿のネズミ」
でも、なぜネズミなのだろう。
大仏殿の入り口は閉ざされているので、連子窓から拝することになる。
 「微かに残る朱の瑞花紋」
「微かに残る朱の瑞花紋」
 「膝の銘文」
「膝の銘文」
さてこの大仏の造立は、真楽寺三世の静室素性が、美濃田村の中川清左衛門と企てた。
完成時期は、「請合申一札之事」に、「元文二年巳六月七日」とあるので、その前後1737年頃と考えられる。先に引いた『伊勢州飯高郡松坂勝覧』に「近年建立」とあったが、同書が書かれたのが1745(延享2)年だから、成る程、まだ出来てから7年しか経っていない。宣長が拝した頃の大仏は、どのようなお姿であったか。
ところでなぜ大仏なのか。その理由を探る手がかりとなるのが、真楽寺の中興開山・陶瑩素範大和尚の存在である。実は、素範はこの寺に入山する前にいたのが伊賀国阿山郡大山田村の新大仏寺であった。そしてそこで、大仏、大仏殿の再興を企てているのである。
東大寺大仏殿を復興した俊乗坊重源が開いた伊賀の名刹・新大仏寺も、中世の動乱、また1635年の山崩れなどで無惨な有様であった。伊賀に生まれた芭蕉は、江戸からの帰省中の1688(貞享5・元禄元)年、立ち寄り惨状を『笈の小文』に描く。
『笈の小文』
この後、芭蕉は故郷に帰り、名吟、
「さまざまの 事おもひ出す 桜哉」
が生まれる。芭蕉45歳の時である。このような新大仏寺の復興を企てた僧・陶瑩素範が真楽寺に入ったのである。
その昔、山号こそ違え同じ真楽寺には丈六(4.85メートル)の木像阿弥陀如来坐像があったという(2012年8月22日付・中日新聞)。ここにもう一度、大仏を据えたいと考えても何も不思議ではない。志は、三世の静室素性に継がれた。
上申書がある。そこには、資金を集める為に1729(享保14)年9月から1732(享保17)年9月まで三カ年、一志郡市場庄村の参宮街道に小屋懸けをし、そこに丈六、原寸大の絵像を懸け喜捨を願いたいと書かれている。大変な苦労である。
最初、大仏は真楽寺の塔頭・長楽寺の管理するところであった。これも宣長の記述通りである。
だがこのように苦心の末に完成した大仏も、明治の廃仏毀釈で長楽寺が廃寺となり、殿舎はその、ままに、台座ぐらいは壊したのだろう、仏像は真楽寺に移された。
維新の騒ぎも落ち着き、1876(明治9)年には、有志により大仏殿に台座も新造され、無事に大仏は安置された。
なお真楽寺、美濃田の大仏については、『一志郡史』下巻(森田利吉執筆)が詳しい。
大仏のある真楽寺の歴史は古い。
「勢州一志郡美濃田村美堂山真楽寺縁起記」(1711年3月通玄著)には、桓武天皇勅願により伝教大師開創。北畠政具祈願所寺領二十貫とある。
それも戦乱で失われ衰亡。1644(正保元)年になって真覚和尚が再び開基した。中興開山が新大仏寺から迎えた陶瑩素範大和尚である。この時に真言律宗(御室派)となり、本尊は薬師如来で、山号も「美堂山」から「薬王山」に改まった。陶瑩素範の棟札には、「宝永七(1710)年四月八日」に建立し、大工は継松長左衛門、継松伝左衛門であったと記す。
次は、その大仏よりもっと古い時代の話である。
敏太(みぬた)神社は、大仏の隣にある神社である。というより、大仏があった長楽寺は敏太神社、ここは長く八幡宮と呼ばれていたが、その別当寺であった。大仏は八幡宮の祭神の一つの本地仏として作られた。
『延喜式』は、平安時代の905年の勅により編纂された儀式書、法令集で、そこに全国の大事な神社2861社の名前を記したリストが載る。「神名帳」という。名前が乗る神社を「式内社」と呼ぶ。中に「伊勢国一志郡、敏太神社」の名前もある。
神名帳に載るかつての名社も、長く続いた中世の混乱期に、多くはその名前も場所も人々の記憶から消えてしまい、後世、その比定で複数の候補地が挙がるというもったいない有様となった。このような神社を「論社」と呼ぶ。
敏太神社も、「論社」の一つであった。かつて所在した場所の有力候補として、津市久居戸木町にある敏太神社が挙がっていた。
風早池という大きな灌漑用の池の近くにあったので、一般には「風速社」と呼ばれていた。
さて『延喜式』の古写本の「敏太神社」に「トシダ」と振り仮名が付けられる。これが混乱のもととなった。
「トシ」は「疾し」、風が速いと「風早」を連想し、戸木村はもとは一志郡だったので、今は風早社などと呼んでいるが、実はこれが「敏太(とした)」神社だと考えたのが出口延経の『神名帳考證』であった。
この説に対して敢然と立ち向かったのが本居宣長である。
宣長の説を掻い摘んで紹介しよう。
『延喜式』と同じ平安時代、930年頃に編纂された『和名類聚抄』という百科事典がある。その中の諸国郡名部、伊勢国一志郡に、「民太【三乃太】」とある。「一志郡民太は、ミノタと読む」と言う意味だ。
「敏」という漢字は、呉音では「ミン」と読み、撥音便「ン」がなかった古代の日本では「ミヌ」と発音し、やがて「ヌ」が「ノ」となった。たとえば「美濃国」の「ミノ」は、もともとは「ミヌ」と言っていたはずだというのが、宣長の説である。
実際に『万葉集』では、「敏馬乃埼」(389番歌)など「敏」を「ミヌ」と読む。
よそ道に逸れるが、宣長の高弟・小篠敏は、オザサミヌである。
さらに脇道だが、では宣長の娘・美濃は「ミヌ」さんか、「ミノ」さんかと問われると、答は保留したいのだが、ここでは郷名の「民太」も、神社名の「敏太」も「ミヌタ」と読む。
宣長は一志郡を見回して、該当する地名を探す。ヒットしたのが「美濃田」である。
随って、『和名類聚抄』の「民太」も、「神名帳」の「敏太」も美濃田村、そこにある神社を指すと考えてよい。以上が宣長の回答である。
なお、『式内社調査報告』第7巻東海道2の「敏太神社」を執筆した西山徳氏は宣長の説をご存じなかったで、戸木説、美濃田説と揺れ動いている。
宣長の説は、「当御領一志郡美濃田村神社事」としてまとめられている。1779(安永8)年7月に、松坂城代・小野藤右衛門殿に提出された文書で、今は『本居宣長全集』14巻で誰でも見ることが出来るのだが、西山氏が原稿を書いた頃には未刊だった。
 「石燈籠の元禄2年銘」
「石燈籠の元禄2年銘」神社は2022(令和4)年3月に式年遷宮を終えたばかりである。
 「案内板、美濃田大仏への道」
「案内板、美濃田大仏への道」
 「美濃田へ大仏に続く竹林」
「美濃田へ大仏に続く竹林」カチっと松坂 本居宣長の町|2024.11.1
前 本居宣長記念館 館長
國學院大学在学中からの宣長研究は45年に及ぶ
『本居宣長の不思議』(本居宣長記念館) 『宣長にまねぶ』(致知出版社)など著書多数