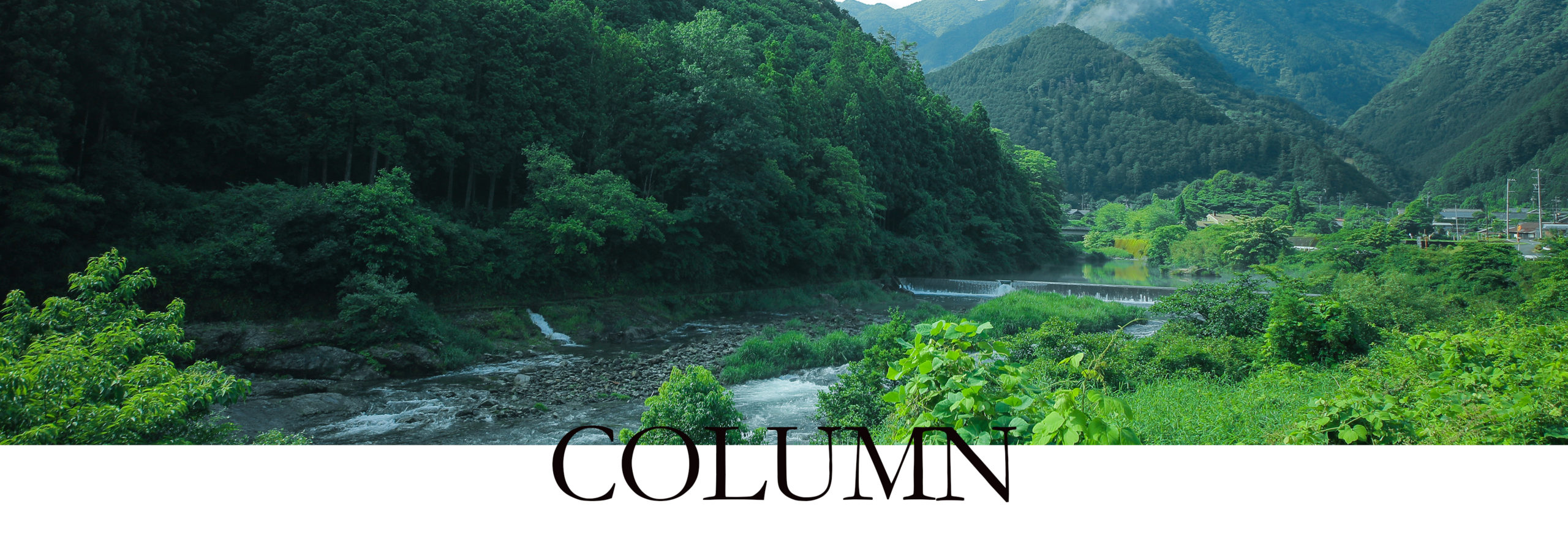
誰かがテレビを見ている。ああNHKの大河ドラマか、今年は蔦重、「べらぼう?蔦重栄華乃夢噺?」、吉原に芝居小屋で浮世絵と太平楽だ、と突然、場面が変わってあれっと思った、主人公・蔦重と思しき男が見慣れた家の前に立っている、どこだ、どこの家、なんだ本居宣長旧宅ではないか。
そうか蔦重は亡くなる少し前に伊勢国松坂の宣長のところにやってきていたなあ、こりゃ見逃しちゃならぬとおもったら、ドラマは大団円。
悪所尽くしの一年間、最後のシーンは鈴の音の松坂魚町本居宣長を訪ねるというのは、誠に洒落たよく考えられたものと感心したが、初夢か、それとも幻視か。
蔦屋重三郎は江戸の本屋である。遊郭・新吉原に生まれ、吉原の案内書「細見」の発行から、江戸でも随一の地本問屋に成長していった。
地本問屋というのは、草紙や浄瑠璃本、芝居絵、絵本、浮世絵(一枚絵)、つまり学術書以外を店先に並べる本屋である。もう少し硬い本を扱うのは書物問屋、物之本屋などと呼ばれた。
地本問屋は上方で言う絵双紙屋である。このコラム22回に載せた大坂の本屋の店先行燈(再現)の写真には、「本、浄瑠璃本、古本、新本」と書いてあった。
当時は江戸日本橋通油町、つまり松坂商人が軒を並べる大伝馬町の一角にあった地本問屋の雄・蔦屋重三郎が宣長を訪問した。つまり軟らかい本の地本問屋から、堅い本の書物問屋への転身、あるいは取り扱い書の範囲を広げようとしたと言うことを意味する。
来訪の事実は宣長の記録に出ている。
「(寛政7年3月)同廿五日来ル
一、江戸通油町蔦(ツタ)ヤ重三郎 来ル
右ハ(加藤)千蔭(村田)春海ナドコンイノ書林也」
『雅事要案』 本居宣長全集20巻269頁
とある。なんだこれだけの記述かと言うなかれ。宣長のこの3月も用事が多い。
少しふり返ってみよう。
1795(寛政7)年3月 宣長66歳
1日、信濃松代藩士・入半之丞真菅がやって来た。
4日、清水伊八から美濃紙10帖が届いた。何かの礼か挨拶だろう。
5日、愛宕の天神さん菅相寺で花見会。近江国栗本郡矢橋浦鞭埼八幡宮神主大神丹後の子、亀之進が扇箱2本を持って挨拶にきた。松坂の殿村寿原さんから白玉饅頭15個もらった。
9日、京都の平子新兵衛から上扇4本が届いた。平子は、宣長の長男・春庭が京都で世話になっている人である。
10日には、『源氏物語』「行幸巻」が講釈終了、次は「藤袴巻」である。
12日頃、『源氏物語玉の小櫛』巻1,2再稿本の執筆に取りかかった。
17日、芝原武二郎が菓子袋を持ってやって来た。
18日、出雲大社の千家清主が出雲特産の「御埼わかめ」をもってやって来た。
19日、吉野飛鳥紀行『菅笠日記』の校正が届いた。皆が刊行を待ちわびている本だ。急いで校正をしないといけない。
26日、日本の外交史をまとめた『馭戎慨言』の校正が届いた。
28日、『古事記伝』巻17の版下(印刷の原本)がやっと書き上がった。頼みの春庭が失明したので自分で書かねばならない。先は未だ長い。
29日、津八幡町の倉田金十郎から「ういろう餅」が届いた。
30日、『大祓詞後釈』を起稿した。この本は神道の最も大事な「大祓の詞」の注釈で、賀茂真淵先生の注を訂正させてもらいましたという遠慮から「後」を書名に付けたが、宣長の主著の一つとなった。神道界への影響が大きかった本。細倉半斎が扇3本、墨1丁をもってやって来た。
この月、月次二十四番歌合の評をした。
次から次へと人が来る。たとえば、扇箱持参でやって来た大神亀之助や、細倉半斎などはその品から入門の志があったかもしれないが、宣長が認めなかったのか、書き漏らしか『授業門人姓名録』に未記載、つまり門人には入っていない。
到来物の書き漏らしも仕方ないだろう。
だが校正は厳密に見落としがあってはならない。
また次の著作の準備も必要だ。
そんな中で、江戸通油町の「蔦(ツタ)ヤ重三郎来ル、右ハ(加藤)千蔭(村田)春海ナドコンイノ書林也」は、私の目からは、ずいぶん丁寧な記載だ。
村田春海と言えば賀茂真淵の弟子の筆頭。あの1763(宝暦13)年、真淵の京・大和の旅にも兄の春郷と同行したが、「松坂の一夜」では宣長とは会っていない。大方、松坂の愛宕町辺りに出かけていたのだろうと噂される江戸十八大通の一人。真淵の死で学問は廃業したと言いながら、宣長の下を訪ねてもいる。
千蔭は、真淵の『万葉集』研究の後継者。父・加藤枝直は、松坂にいた紀州藩士で、吉宗が将軍となった時に大岡忠相に取り立てられ江戸に移り住んだ。宣長には、自分の著作『万葉集略解』の稿本を宣長の手直ししてもらっていて、格別懇意な人である。
その知人であるからぞんざいには扱えない。だが、もっと深い事情があったのではないかと見る人もいる。
抜け目のない商才の蔦重が、春海や千蔭からの紹介を取り付けての松坂入りだ。きっと増田さんの推測は当たっているのだろう。
大河ドラマ「べらぼう 蔦重栄華乃夢噺」の公式HPには、「日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き 時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物 “蔦重”こと蔦屋重三郎の波乱万丈の生涯。笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ!」
とある。主演は、横浜流星で、1月5日にスタート。
果たして12月、伊勢国松坂が登場するかどうかは、見てのお楽しみ。いや、ぜひ登場させたいものだ。ご声援をお願いします。
さて、宣長本が江戸日本橋の蔦屋耕書堂の店前に並んだ。
大伝馬町の松坂店で働く人の大方は興味もなかっただろうが、ご主人クラスは、「おお、宣長さんの本じゃ」と手にしたかもしれない。
これはあり得ない話ではない。小津や長谷川のお店の並ぶ大伝馬町1町目からまっすぐに10分弱も歩けば耕書堂だ。
約30数年前に、江戸から帰ったご主人が、こんな本が江戸では評判だと持ってきてくれたのが賀茂真淵の『冠辞考』、これが宣長の『古事記』研究のスタートとなった。日本橋は、日本国中から人や金、情報が集まる場所。そして本屋は、時代の先端を行く場所であった。発信力は抜群だ。
だが私は、蔦重が宣長のところに来たのにはもっと大事な理由があると思う。
それは、気分転換だ。
クリエイティブな仕事をする人ほどに、休むことは必要だ。
「細見」から富本節、狂歌に今のコミックスの黄表紙、洒落本と「江戸の花」と持て囃されたが、寛政の改革のあおりで洒落本三冊が筆禍に遭い、作者の山東京伝は手鎖五十日、版元蔦屋は身上半減というお咎めをうけた。吉原の不況や色々あったが、十返舎一九を抱え、そして爆発的な人気を博し、後世にまでその影響が及んだ写楽の役者絵である。
時代の最先端を走り続けた蔦重が、立ち止まった。
そして生まれて初めてだろう、箱根の山を越えて伊勢を訪れたのである。
残念ながら、蔦重は次の新企画を打ち出す前、1797(寛政9)年5月6日に脚気がもとでなくなった。享年48。
鈴屋で蔦重はどんな夢を描いたのだろう。
江戸の話には興味津々だったという宣長だが、どんな話を蔦重から聞いたのだろう。
さて宣長だが、やはり長期の休暇を取ったことがある。
『古事記』上巻、神代巻の注を書き終えた49歳から2年半、『古事記伝』執筆を中断したのだ。神武天皇から始まる人の世に移る時期である。神から人へ、頭を切り換えていくのである。執筆は中断したが、猛烈に本を読み、写している。もちろんこの間も医業も怠りなく、休養2年目の安永9年には、薬料収入95両、調剤数8429服、再開する天明元年には薬料96両、調剤数8165服を計上するのである。記録に残る生涯最高所得である。
次回は、この宣長の2年半の休養についてお話ししてみたい。
カチっと松坂 本居宣長の町|2025.01.1
前 本居宣長記念館 館長
國學院大学在学中からの宣長研究は45年に及ぶ
『本居宣長の不思議』(本居宣長記念館) 『宣長にまねぶ』(致知出版社)など著書多数